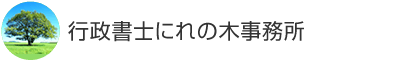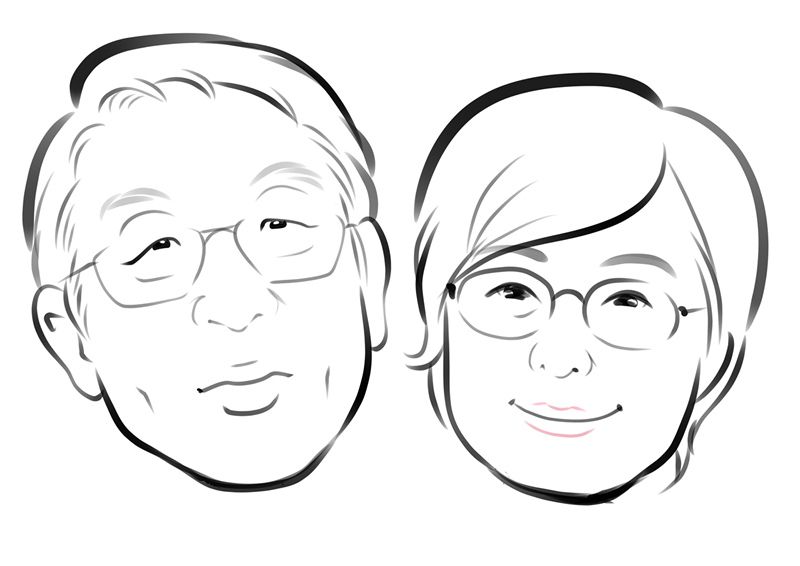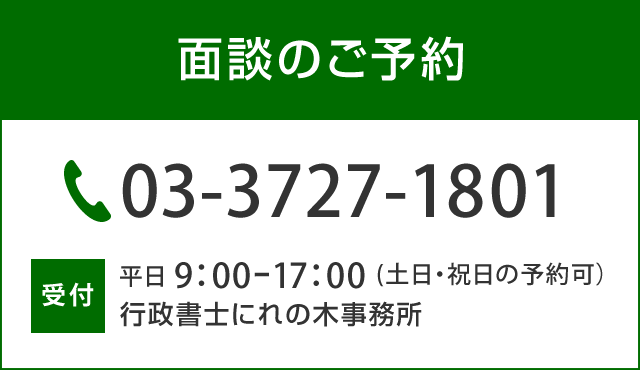目次
どれだけの人が、相続によって土地や家などの積極財産と共に、債務それも保証債務など消極財産が承継される事を知っているであろうか?又、相続放棄できるのが、相続開始後3ヶ月という短い期間であることを認識しているであろうか?相続放棄の有効性に関する多くの裁判例から読み取れるのは、殆どの人がこれらの事を知らないという事と、少なくない方々が、自分には直接責任のない債務の弁済を迫られて苦しんでいることである。ここでは、裁判例の要約を説明するが、本HPの他のページに、債務の承継と相続放棄のやり方について詳細な説明があります。
- 債務は法定相続分で自動的に承継ー積極財産の相続分とは無関係
- 相続放棄で債務から逃れる方法ー配偶者と子の場合を解説
- 相続放棄で債務から逃れる方法ー兄弟姉妹・直系尊属の場合を解説
- 家裁で手続しない相続放棄は相続権の放棄ーはんこ代目当てが殆ど
相続において、金銭債務は、法定相続分に従って当然に分割され、相続人に承継されます。相続により積極財産だけでなく、消極財産も相続人に承継されます。被相続人の消極財産が積極財産を上廻る場合には、債務を免れるため相続人が相続放棄の申述手続をする事が必須です。
しかし、債務、とりわけ、保証債務は表に出てきにくく、相続人にその存在が判明するまで時間がかかるため、どの時点まで有効な相続放棄申述が認められるかが深刻な問題となります。家庭裁判所において相続放棄申述が認められる期間を「熟慮期間」と言い、3ヶ月間しかないためにその起算日について多数の裁判例が積み重ねられています。
民法915条は、熟慮期間は「自己のために相続が開始したことを知った時から三箇月」と規定され、この3ヶ月間で被相続人の財産状態を調査して相続の承認か放棄の選択することとされています。(熟慮期間は家裁に審判を申立てて伸張することができます。)しかし、被相続人との交流が殆どない等生活関係が希薄な場合などは、被相続人の財産状態、特に債務、とりわけ保証債務を調査することは困難を極めるのは当然なので、熟慮期間の起算日をいつとするかが生命線となります。心ならずも自らと直接関係のない多額の借財を負ってしまうという悲劇も少なくありません。
熟慮期間の起算日である「自己のために相続が開始したことを知った時」とは、「①相続の原因である事実(死亡等)を知った時及び②これにより自己が法律上の相続人となったと知った時」とする判例(大審院決定大正15.8.3、単に死亡等の相続開始の原因事実を知っただけで足りるとした判例を変更)が確立していて、これが熟慮期間の起算日の原則です。自己が法律上の相続人となったと知った時の要件から、兄弟姉妹等の第三順位の相続人は、前順位の相続人全ての相続放棄を知った時や相続債権者から催告や支払督促を受けた時が起算日となります。
この原則に対する例外を認容すべきかどうかを争点にして、昭和59年4月27日の最高裁判例をリーディングケースとして、相続放棄申述受理審判及び訴訟における多くの裁判例があります。

昭和59年の最高裁判例は、①被相続人に全く相続財産がないと信じ、②被相続人との生活歴等から相続財産の調査に困難な事情があって相続財産がないと信じた事に過失がない時は、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識しうべき時から起算とすべきと判示しました。
- 相続放棄の熟慮期間・起算日の例外措置を認める先例となる裁判例(最二判昭和59年4月27日)
この最高裁判例をめぐっては、文字通り「相続財産が全くない」と信じた場合に限るという限定説と、一部相続財産の存在を知っていても通常は債務の存在を知れば当然相続放棄したであるような「債務が存在しない」と信じた場合も含まれるという非限定説があります。
訴訟は限定説をベースに解釈され、相続放棄の申述受理審判では非限定説をベースに運用されているという主張・言説もあるようですし、最高裁は限定説に立つという解釈もあるようです。現に、原則受理の考え方を明言した高裁・抗告審の決定例も数例ありますが、すべての受理審判がこの説に従っているかどうかは不明です。
現実には、相続申述受理審判においては、大半の申立てが受理されているようです。しかし、受理審判で受理されても、「熟慮期間後の申述」や「単純承認と見做される事実がある」など法律上の無効原因があるとして相続債権者から訴訟が提起された場合、受理審判には、訴訟でも有効な相続放棄申述とされる既判力がなく、その相続放棄の有効性は、最終的に訴訟で判断されます。一方、受理審判で却下されてしまうと相続放棄の道は完全に閉ざされ、債権者が起こす債務履行を求める訴訟で、相続放棄申述を理由に債務を免れることができなくなります。
従い、相当額の債務リスクの可能性がある場合は、まずは熟慮期間の伸張を行って、その間に徹底的な調査をすべきです。特に自らの会社を経営したりしていた被相続人は、個人保証の有無や内容を十分に調べるべきです。
その上で、債務リスクが大きい場合は、膨大な時間と費用がかかる訴訟に持ち込まれるリスクを考慮して、極力、原則の相続開始後3ヶ月以内に相続放棄申述をすべきです。又、自分は相続財産はいらないというケースでは、安全サイドに立って家庭裁判所で相続放棄の申述をすべきです。(3.1.1、3.1.4、3.1.5は、相続財産はいらないケースの裁判例)相続財産はいらないが、はんこ料的な代償金は欲しいという場合は、承継相続人との間で、相続放棄申述の法律行為の代償金契約を作成後に、正式な相続放棄申述を行うべきでしょう。
尚、相続開始後に相続人が死亡した時は、相続人としての地位は、甥・姪や孫など当該相続人の相続人に承継されます。一代上からの相続人の地位の承継は「再転相続」と呼ばれ、熟慮期間の起算日には民法916条が適用されます。
甥・姪や孫などは、通常、被相続人との生活関係が、兄弟姉妹や子などより希薄な上に、自分の親からの相続は認識してもその一代上からの相続人の地位の承継については気づかない場合も多く、再転相続における熟慮期間の起算日はより深刻な問題になりがちでした。最高裁判所の令和元年8月9日の判例は、再転相続人である丙が、乙の甲に対する相続人としての地位を承継した事実を知った時を起算日とする解釈を明確にしました。

1.相続放棄の申述受理審判の性格
1.1受理審判の法的効果
債権者等から提起される訴訟において、相続放棄が有効であると認められる効力(既判力)はありません。従い、家庭裁判所が相続放棄を受理しても、債権者にも相続放棄が有効だと認めさせる強制力はありません。債権者等は、熟慮期間徒過後の申述や法定単純承認(民921条)と見做される事実の存在などを理由として債務履行を求める訴訟を提起することができ、訴訟において有効性の可否が判断されます。
1.2却下審判の法的効果
受理審判が訴訟でその有効性を争われる余地があるのに対し、不受理の審判が下りると訴訟での救済措置はありません。債権者からの履行請求訴訟では、相続放棄以外の事由(契約の無効や不存在等)を立証する以外は、債務を免れる道はなくなり ます。
1.3受理審判の審理範囲
相続放棄申述の実体的要件は、①法定の様式を具備していること②相続人であること③法定の熟慮期間内であること④相続人の真意があること⑤法定単純承認となる事実がないことですが、家庭裁判所がどの範囲まで審理すべきかについては定説がありません。
問題となるのは、③と⑤です。却下されて不受理となると、もはや、相続放棄をする余地がなくなるという強い効果があるので、相続放棄申述は原則的に受理すべきで、実体的要件に明白な瑕疵がある場合のみ不受理とすべきとの原則受理説も主張されています。現に、そういう考え方を表明した高裁・抗告審の決定例も数例あります。債権者は、秘蔵族人の資力を考慮して取引していて、相続人の資力をあてにしているわけではなく、原則受理しても、相続債権者に不利益はないとの考え方がベースになっているようです。
1.4裁判所HPでの説明
裁判所HP中の裁判手続案内中に「相続の放棄の申述」についての説明があります。「9.手続の内容に関する説明」に以下のようなQ&Aが記載されていますが、2.で述べる最高裁判例をそのまま引用しているようです。但し、相当な理由があるときなどは、受理されることもありますと、多少、含みをもたせた表現をしています。
Q :夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。
A :相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
-1024x683.jpg)
2.熟慮期間起算日判断の基礎となる最高裁判例(最二判昭和59.4.27)
定職につかずギャンブルに熱中していた被相続人Aに愛想を尽かした妻と子が、12-3年前に別居し没交渉となった後に、Aの生活保護を扱う民生委員の連絡を受けた子の一人が立ち会ってAが病院で死亡し、他の子や妻もAの死亡後直ぐに相続開始を知った。
何の相続財産もないと思った相続人は何の手続しなかったが、相続開始から11ヶ月後に債権者から保証債務の履行を求められた。相続人は、直ちに相続放棄の申述を行い約2ヶ月後に受理されたが、債権者が、熟慮期間経過後の無効な相続放棄であり、保証債務の相続による承継を主張して訴訟を提起し、最高裁まで争われた。
「相続人は、相続開始後すぐに相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に全く相続財産がないと信じたためであり、被相続人との生活歴や交際状態等からみて相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人がそう信ずるについて相当な理由があると認められる時は、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と最高裁は判示して、相続人の相続放棄の申述を熟慮期間内の適法なものとしました。(但し、判事5人中1人の反対意見あり。)
- 相続放棄の熟慮期間・起算日の例外措置を認める先例となる裁判例(最二判昭59.4.27)
3.相続放棄の申述受理審判における裁判例
3.1受理例
「相続財産はいらない・自分の相続財産はない」と考えていたケースは、3.1.1、3.1.4と3.1.5。「相続財産は全くない」と信じていたケースは、3.1.2と3.1.3。
3.1.1仙台高裁決定平元9.1(家裁月報42-1-108)
被相続人Aは、宅地以外に田畑を所有して、Aは大工として、妻が主として農作業に従事する兼業農家を経営し、長男と同居していた。長男は、建築会社を経営し、Aを名目上の債務者(Aは会社の取締役)として、A所有の不動産に根抵当権を設定して、会社の運転資金を農協から借入れた。相続開始時の債務総額は2762万円。
相続人は、相続財産として不動産があることを認識していたが、相続放棄は行わず、相続開始後8ヶ月後に農協から履行請求を受けて、履行請求を受けた3ヶ月後に相続放棄申述を行った。原審の福島家裁郡山支部は却下した為、高裁に即時抗告した。高裁は、下記理由から原審を取り消し、相続放棄の申述を受理。
- 相続放棄は自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させる意思表示で、極めて重要な法律行為であるので、家庭裁判所に後見的に関与させ、専ら相続放棄に真意を明確にして、相続関係の安定を図る制度。
- 相続放棄申述の受理審判に当っては、法定単純承認の有無、熟慮期間経過の有無、詐欺その他取消原因の有無等の実質的要件の存否について、申述書の内容、申述人の審問の結果、家裁調査官による調査の結果等から、申述の実質的要件を欠いていることが極めて明白である場合に限り、申述を却下するのが相当。
- 相続放棄申述受理審判は非訟手続で、最終的に相続関係及びこれに関連する権利義務が最終的に確定するものでないうえ、受理審判が却下されると、相続人には相続放棄する途が閉ざされるので、実質的要件については、その不存在が極めて明らかな場合に限り審理の対象とすべき。
- 相続人は、農家なので不動産は長男が取得するもので自己が相続で取得するものはないと信じかつそう信じるたことに無理からぬ事情があることが窺われるので、農協から請求を受けて債務の存在を知った時を(熟慮期間の)起算日と解する余地がないわけでないので、受理するのが相当。
農家なので長男だけが相続すると考えていたケースで、そうであれば、相続放棄申述を行っても何のデメリットのない事案であった。
3.1.2福岡高裁決定平2.9.25(判例タイムズ742-159)
被相続人Aは昭和63年10月28日死亡し、相続人は妻と子の2人。Aは会社退職後は年金生活で、住居は借家で預金など財産と呼べるものは何も残していなかったので、妻と子は相続のことなど頭に浮かばなかった。
Aは、妻と子には話さずに、昭和54年に50万円の貸金の連帯保証人となっていて、相続人2人は平成元年11月28日に同月24日付け承継執行文を付与した公正証書謄本の送達を受け、同年12月12日ころ債権者から書面で履行請求されたので、相続放棄の申述をした。福岡家裁小倉支部は熟慮期間を徒過したとして不受理とした。福岡高裁に即時抗告したが、高裁は、下記理由から、原審判を取り消し、申述受理手続のために家裁支部に差し戻した。
- 家庭裁判所は、相続放棄の申述に対して、申述人が真の相続人であるか、申述書の署名押印等法定の方式が具備されているか、3か月の熟慮期間内の申述かどうかの実質的要件も審査することができると解するのが相当である。
- しかし、相続放棄の申述の受理が相続放棄の効果を生ずる不可欠の要件であること、不受理の効果が大きいこととの対比で、却下審判に対する救済方法が即時抗告しかないのは抗告審の審理構造からいって不十分。
- 熟慮期間の要件の存否について家裁は一応の審理で足り、その結果同要件の欠缺が明白である場合のみ却下すべきで、それ以外は同申述は受理するのが相当。
- こう解しても、債権者は後日訴訟手続で相続放棄申述が無効であるとの主張ができるから、相続人と利害が対立する債権者に不測の損害を生じさせることにならない。
- 対立当事者による訴訟で十分な主張立証を尽くさせた上で有効無効を決する方がより当を得ている。
- 3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、こう信じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算日は、相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかり時とするのが相当。
最高裁の昭和59年4月27日判決をベースとしながら、3.1.1と同様に、原則受理説に立っている決定と見做すことができるようである。
3.1.3仙台高裁決定平8.12.4(家裁月報49-5-89)
被相続人Aは、生前、いか釣り漁の船主をしていたが、経営が苦しくなって、平成4年に正式な廃業手続をした。Aの負債整理のため、○信用金庫がAの自宅不動産の競売手続に入ったが、相続人らが資金を拠出して自宅不動産を買い取った。
Aは自己破産手続はせずに、平成7年11月に死亡した。相続対象となる資産はなかったので、同一敷地内に居住していた相続人3人は、相続放棄手続はしなかった。平成8年3月になって△銀行から1億円の負債があることを知らされ、相続人が調査したところ、銀行以外にも、×漁協から9000万円の借入金及び資材等の残債4500万があることを知った。平成8年4月に青森家裁八戸支部に相続放棄の申述をしたが、受理を却下され、仙台高裁に即時抗告した。高裁は、下記理由から、原審判を取り消して、家裁支部に差し戻した。
- 家庭裁判所が相続放棄の申述を不受理とした場合の不服申立ての方法としては、高等裁判所への即時抗告だけが認められているにすぎず、不受理の効果に比べて、救済方法が必ずしも十分とはいえない。
- 従い、家庭裁判所において、その申述が熟慮期間内のものであるか否かを判断する場合は、その要件の欠缺が明らかであるときに、却下すべきとしても、その欠缺が明らかと言えないような時には、その申述を受理すべきと解するのが相当。
- このように解しても、被相続人の債権者は、後日、訴訟手続で相続放棄の効果を争うことができるので、債権者に対して不測の損害を生じさせることにならない。
3.1.1と3.1.2と類似した原則受理説に立っているように思われる決定例。被相続人が生前漁船を船主をして経営不振から廃業手続を行い自宅が競売措置を受けていて、殆ど相続すべき財産がない事案。相続財産がないだけでなく、むしろ、生前の事業経営で、潜在的な債務や保証債務等があることを予想して相続放棄すべきだった事件。遺族が、相続の対象は積極財産だけで、相続で債務は承継しないと考えていた可能性大。

3.1.4東京高裁決定平12.2.7(家裁月報53-7-124,判タ1051-302)
被相続人A(会社の創業者)は、平成4年に債務を含む遺産すべてを長男B(Aから会社経営権を承継)に相続させる旨の公正証書遺言を作成して、平成7年10月26日死亡。Aの長女Xは、自分が相続する積極・消極財産は全くないものと考えて相続放棄の手続及び遺留分減殺請求手続もしなかった。
A死亡から2年以上経過して、B承継の会社が倒産し、平成9年Bは自己破産した。その後平成12年6月17日に、Bが相続したA購入のマンション購入に充当されたY公庫よりの住宅ローンの催告書がXに送付されて、法定相続分のローン債務をXが承継したことを知る。(BとY公庫との間で、可能であったBの単独債務とする手続はなされず。)、Xは同年8月30日に相続放棄申述したが、原審の家裁は、XがA死亡時点で相続財産が存在したことを認識していたので、自己が相続しないと理解したたとしても、熟慮期間は相続財産の認識の時から進行するとして却下したので、東京高裁へ即時抗告した。高裁は、下記理由から、原審判を取り消し、申述受理手続のため差し戻した。
- (熟慮期間の起算日について昭和59年最判を引用した上で)Xが、公正証書遺言があるので自分は積極・消極財産を全く承継しないと信じたことについて遺言の内容等に照らし相当な理由があった。
- Xが、Aの相続開始後に所定の熟慮期間内に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することはおよそ期待できなかったし、死亡を知っただけでは自己のために相続があったことを知ったとはいえない。
- 相続開始時に相続財産があることを知っていたとしても熟慮期間は進行せず、Y公庫からの催告を受けて初めて債務を相続する立場にあることを知ったので、催告時から所定の熟慮期間内の放棄申述は適法。
全く相続財産がないと信じ、又遺留分も含めて一切の積極財産をいらないと考えていたXは、やはり、Aの死亡後3ヶ月以内に相続放棄の申述をしておけば、こんなややこしい事件に巻き込まれて、時間も費用も浪費することは避けられたであろう。元々、相続財産はいらないと言うことなので、XはA死亡後3ヶ月以内に相続放棄申述をしても、何のデメリットも生じなかった。
3.1.5東京高裁決定平26.3.27(判時2229-21)
【事案の概要】
被相続人Aは、平成22年8月8日死亡し、その相続人は、長男B、長女X1及び二女X2。Aは、生前、自宅である土地建物ほかの不動産を所有し、BのC信用金庫に対する貸金債務を連帯保証していたが、 X1及びX2は連帯保証のことは知らなかった。Aは、生前、同居しているBに自己の財産全部に譲る意向を示していて、X1もX2もAからこの意向を聴いて何の異議も唱えなかった。(Aは遺言書を作成せず。)
X1もX2も、A所有の不動産があることは知っていたが、Aの保証債務の存在は知らず、BがAの相続財産一切を相続したので、自分たちが相続するものはないと考えていたので、X1もX2も相続放棄の申述はもとより、Bとの間で遺産分割協議もしなかった。
X1及びX2は、Bから、移転登記のため「遺産分割協議証明書」に署名押印してほしいと頼まれ、平成24年2月20日頃に応じた。この書面には、「共同相続人全員で分割協議をした結果、相続財産に属する不動産はBが取得したことを証明する」との記載がある。X1及びX2は、この書面作成により、Bが相続財産全てを取得し、自らはAの相続について放棄したと考えていた。
Bは平成25年3月ころ、相続した所有不動産の一部を売却してC信用金庫に対する貸金債務の弁済に充て、Cの同不動産に対する根抵当権を抹消をしようと考えた。C信用金庫は、Bに対してX1及びX2が保証債務履行責任を承知している旨の承諾書を提出するように求め、BはX1及びX2に無断で承諾書を提出した。(BのC信用金庫への債務は数本あり、一部不動産の売却収入だけで全貸金を弁済できていない。)Bは、X1及びX2に対して、C信用金庫から確認の電話があったときは承諾書を承知している旨答えるよう依頼した。X1及びX2は不審に思って調査した結果、AがBのC信用金庫に対する貸金債務を連帯保証していて、相続債務としてこの保証債務があることを始めて知った。
X1及びX2は、平成25年4月2日、長野家庭裁判所に、相続開始を知った日はAの連帯保証債務の存在を知った同年3月とし、放棄の理由として債務超過、負債不明と申述書に記載して、相続放棄申述をした。原審は、熟慮期間が徒過しているとして、受理を却下した。
【判示事項】
X1及びX2は、被相続人が死亡した当時被相続人の相続財産に不動産があることを知っていたものの、被相続人の意向も聞いていて、長男であるBが不動産を含む被相続人の相続財産全てを承継し、自らには相続すべき被相続人の相続財産がないものと信じていたことが認められる。また、被相続人の意向、被相続人とX1及びX2との生前の交流状況からすると、X1及びX2が上記のように信じていたことについて相当の理由があったことも認められる。
「遺産分割協議書」に署名押印し、Bに送付又は交付したことが認められるが、上記書面は、被相続人の相続財産の不動産についてBの名義に移転登記するためにBに送付等されたものであり、現実に遺産分割協議がされたものではないから、この書面の送付等をもって、自己のために相続の開始があったことを知ったものと認めることはできない。(この点に関する経過の詳細等については、訴訟が提起された場合にその訴訟手続内において判断されるべきである。)
その後、X1及びX2は、Bから承諾書について依頼を受けて後にC信用金庫への問い合わせしたこと等により、C信用金庫に対する貸金債務についての連帯保証債務の存在を知ったので、本件における熟慮期間の起算日は、X1及びX2が連帯保証債務の存在を認識した平成25年3月26日とするのが相当。したがって、同日から7日後に行ったX1及びX2の各申述は、熟慮期間内の申立てで、受理するのが相当。
【コメント】
作成された遺産分割協議書は、移転登記のための形式的書面(登記原因証明情報)にすぎず、実際の遺産分割協議はなかったと認定したもので、保証債務の存在を知った時を熟慮期間の起算日とした審判例である。
「現実に遺産分割協議がされたものではない」と本決定は認定しているが、一方「経過の詳細等は訴訟手続内で判断されるべきもの」ともしており、債権者から保証債務の履行請求を求めて訴訟が提起され、遺産分割協議を経ていると認定された場合は、申述却下の判決が下る可能性も否定できない。
3.1.3の東京高裁決定平12.2.7と同じことが言えるが、Aの死亡後3ヶ月以内に相続放棄の申述をしておくべきだった。X1及びX2は、相続財産は実際にいらないので、相続放棄の申述をしても、何のデメリットも生じなかった。
-1024x682.jpg)
3.2不受理・却下例
3.2.1高松高裁決定平13.1.10(家裁月報54-4-66)
平成9年3月に被相続人Aは死亡。唯一の相続人でAの養子であるXは、Aの死亡日に相続開始の事実を知り、相続財産として宅地(20坪)・建物(10坪)及び預金15万円があることを知っていた。Xは上記預金を葬儀費用(約18万円)のに充当した。
Aは、Xに知らせずに、甥の住宅金融公庫からのローンの連帯保証人となっていた。平成12年の甥の死亡後に、甥の相続人全員が相続放棄したので、公庫は、平成12年11月20日に電話で連帯保証人Aの相続人であるXに5500万円の保証債務の履行を催告した。Xは、平成12年11月22日に、高松家裁丸亀支部で相続放棄の申述を行ったが却下された。高松高裁に即時抗告したが、高裁は下記理由から棄却。更に、Xは最高裁に許可抗告したが、平成13年10月に棄却して確定。
- 熟慮期間は、遅くとも相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき。(最高裁昭和59年4月27日判決、2に記載)
- Xは、被相続人の死亡をその当日に知り、それ以前に相続財産として宅地・建物・預金15万円があることを知っていたから、被相続人の死亡の日に相続財産の一部の存在を認識した。したがい、熟慮期間は平成9年3月から起算。
- 原審は、預金15万を相続していることも却下の二つ目の理由としていたが、高裁はこの理由を削除し、相続財産の一部を認識した時が死亡日だったことのみを却下理由とした。
尚、Xの代理人は、最高裁への許可抗告申立て理由書に以下主張を行ったが、最高裁の認めるところとはならなかった。下記代理人の主張は、リーズナブルで、もっと尊重されてしかるべきだったと思う。
- 社会常識上、一般通常人が判断する場合、積極財産が515万(不動産の評価は500万)で、消極財産が5500万以上も存在する前提事実であれば、誰でも相続放棄する。保証債務であれば、主債務者(Aに甥)の履行可能性を必ず調査する筈。
- 消極財産5500万の存在は、単純承認もしくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき最も重要な前提事実であり、この事実を知った時又は通常これを認識しうべき時から熟慮期間を起算すべきである。
3.2.2東京高裁決定平14.1.16(家裁月報55-11-106)
被相続人A死亡の7日後の平成10年1月9日に、相続人が遺産分割協議をして、A所有の不動産を長男X1に単独取得させることで合意し、長男以外の相続人(X2~X3)は相続分不存在証明書に署名押印してX1に渡した。
A死亡後約3年7月を経過後の平成13年8月24日に、銀行が7000万円を超えるAの連帯保証債務の履行を求める訴訟を提起した。Xらは訴状を送達されて初めてその債務を知ったとして、平成13年10月24日 に相続放棄の申述を千葉家裁八日市場支部で行ったが、却下された。東京高裁に即時抗告したが、高裁も下記理由から棄却。更に、最高裁にも許可抗告したが棄却された。
- 相続の承認又は放棄に係わる3ヶ月の熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべき。
- 3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄しなかった原因が、被相続人との生活歴、被相続人と相続人の間の交際状態などからみて当該相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において自己が相続すべき遺産がないと信じたためであり、かつ、そのように信ずるについて相当な理由があると認められる時は、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起 算すべき。(最高裁昭和59年4月27日判決)
- 本件では、被相続人が死亡した直後の平成10年1月9日ころ、被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で相続人全員で協議し、これを長男に単独取得させる旨合意し、長男以外は相続分不存在証明書に署名押印した。このことは、遅くとも同日ころまでには、相続人全員が、被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識し、相続すべき財産がないと信じたとは認められない。熟慮期間の起算日は、平成10年1月9日の翌日になるので、平成13年10月24日付け相続放棄申述は、熟慮期間を経過した後になされたもの。
- 相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって始めて、相続の開始を知ったといえる旨の抗告人代理人の主張は、独自の見解であり、採用できない。
本件のポイントは、死亡後7日後に実質的な遺産分割協議をして、すべての相続人が被相続人の財産を具体的に認識して単純承認をしたと高裁が認定したことにあろう。実質的な遺産分割協議をして、すべての相続人が法定単純承認したと見做し得る事情があることが、抗告棄却の理由となったのではないか。しかし、3.1.5に記述した東京高裁平成26年3月27日決定では、遺産分割協議証明書まで作成していても、形式的な書面作成であり、実質的な遺産分割協議はなかったとしていることとのバランスはとれていない。本件も類似した事件であり、相続開始後7日後の協議は、実質的遺産分割協議ではなかったと認定する余地はあったのではないか。
3.2.3最高裁の立場
上記2例がいずれも最高裁に許可抗告され、棄却されたことから、最高裁の立場は限定説であると主張する言説があります。しかし、最高裁の2つの決定は、一般法理を示して法律と同等の規範性を有する法理判例ではなく、当該事情と同様の事情があった場合に適用される法理を明らかにする事例判例であり、必ずしも最高裁が限定説に立っているとは明確には言えないとの考え方もあります。
4.訴訟における裁判例
4.1有効性の肯定例
4.1.1東京高裁昭和61.11.27判決(判タ646-198)
被相続人Aは不動産事業を営み、不動産事業において取引慣行に反する不適切な取引行為を行っていたが、相続人Y(養子と長女の二人)はその事を認識していなかった。昭和59年2月24日死亡後の10ヶ月後に、YはAの不法行為による損害賠償請求の訴状の送達を受けた。Yはその11日後に相続放棄の申述をし、家裁で受理された。債権者Xは、YがAの損害賠償債務を承継したとして訴訟を継続した。
Yが訴状送達時までAには相続財産が全くないと信じたことは認定され、Yの勤務状況、年齢等の具体的事情から、そう信じたことはやむを得ないものとして、Yには相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であったから、59年最判のいう「相当な理由」ありとして相続放棄を有効とした。
本件は、不動産取引における被相続人Aの地位の承継から生じる債務の承継が争点である。生前の被相続人の取引行為に対して、相続開始10ヶ月後に訴訟を提起された事例である。相続開始時には、未だ損害賠償債務が確定していないのみならず、訴訟も提起されていない事情の下では、生前の被相続人の取引行為から生じる潜在的債務は、相続人には認識しようがないのではないか。潜在的債務を認識することは不可能に近く、相続財産が全くないと信じたという要件がなくても、相続放棄を有効としてもいいのではとも考えられる。
4.2有効性の否定例
4.2.1大阪高裁平2.11.16判決(判タ751-216)
Bは自己の会社の経営資金を金融機関から借入れており、その担保としてX(信用保証会社)と信用保証委託契約を締結し、Bの夫Aが連帯保証していた。Aは昭和60年8月21日に死亡したが、相続人はB、C(長男)及びY(二男)の3名であった。昭和63年に至ってBが金融機関への返済を怠ったため、Xは金融機関に代位弁済した後、Aの連帯保証債務を承継したB、C及びYに求償請求した。Yは直ちに相続放棄したが、相続開始の約3年後にした相続放棄の申述の効力がXY間で争われた。
Yは昭和55年から家族と離れて生活していて、会社員であるAが死亡当時保証債務を負っていることを知らず、遺産として建物があること及び会社経営の母Bに債務のあることは認識していた。Aと同居していたCらに遺産分割を委ねて自らは、事実上相続を放棄する趣旨で実印と印鑑証明書をBに渡し、遺産であるAの土地建物については昭和60年11月29日付けでC名義に相続登記された。
1審は、相続すべき債務の存在を知らないことに相当の理由がある場合には、相続放棄の可否を自由かつ合理的に決定し得る程度に相続財産の全容を認識し得た時又は通常認識しえたはずの時から熟慮期間が起算されるとして、相続放棄を有効とした。
控訴審の本判決はこれを破棄。相続人Yは遺産の存在を知っていて、債務を含め相続財産の内容の確認も容易であった。熟慮期間の起算点をAの死亡により自己が相続人となったことを知った時以外とする理由はなく、熟慮期間の起算日を繰り下げる特段の事情は認められないとして、相続放棄を無効とした。
4.2.2大阪高裁平21.1.23判決(判タ1309-251 )
被相続人Aは平成15年3月25日死亡。その後3か月経過後の同年12月25日、相続人間で遺産分割協議成立。その際Aには不動産等の積極財産及びX以外に対する約7600万円の債務(消極財産)があるが、積極財産が消極財産を若干上回るとの見通しの下で、Yは不動産の一部や債務の一部を相続した。
ところが、平成19年6月8日に本件訴訟(XのAに対する貸付金に対するAの相続人Yへの弁済請求)が提起され、債務が元本だけで約3億円以上あることが判明した。そこでYは同年7月11日相続放棄の申述をし、受理された。
本判決は、Yは、Aが死亡した時点で、Aの相続財産の有無及びその状況等を認識できるような状況にあった。(少なくともAに相続財産が全くないと信じるような状況にはなかった。)「Aに積極財産及び消極財産があることを認識して遺産分割協議をし、不動産の一部について相続登記も終了して債務も弁済していた事情に照らせば、本件訴訟提起まで本件債務のあることを知らなかったとしても、熟慮期間を本件訴状送達日から起算すべき特段の事情があったとはいえない」としてYの相続放棄を無効とした原判決を維持し、控訴棄却。
本件では、遺産分割協議が終わった上に、それに基づく相続移転登記も行われていた事は、法定単純承認の要件を十分満たすものではないか。

5.再転相続と熟慮期間起算日の最高裁判例(最判令元.8.9)
甲の相続人乙が、甲の相続について承認や放棄をしないで死亡したときは、甲の相続人である乙の法律上の地位が、乙の相続人丙に承継されます。これらの事態は、再転相続、数次相続と言われ、丙は再転相続人とか二次相続人と呼ばれます。(甲の相続開始前に乙が死亡していた場合は、丙は代襲相続人となって、異なる取扱になります。)
丙は乙の法律上の地位を引き継ぐので、何も規定がないと、乙が自己のために相続開始があったことを知った時から2ヶ月経過していた時は、丙の熟慮期間は1ヶ月しか残っておらず、おかしな扱いになってしまいます。
そこで、民法916条が規定され、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間<熟慮期間>は、その者の相続人が自己のために相続の開始があった事を知った時から起算する。」として、丙が自己の相続があった時から起算することとして、乙が相続開始を知った時から経過した時間は算入しないこととしています。
しかし、丙が「自己のために相続の開始があった事を知った時」の解釈をめぐっては、①丙が自分のために乙からの相続(2次相続)を知った時、②丙が乙のために甲からの相続(1次相続)を知った時のどちらであるかは争いがあり、学説の通説は、①の2次相続説でしたが、最高裁は、令和元年8月9日の判決で、②の1次相続説をとることを明確にしました。
(判例掲載誌:判タ判タ1474-5、家庭の法と裁判28-69)
5.1事件の概略
被相続人Aは、F会社の債務に対する連帯保証人の一人になり、G銀行から保証債務の履行請求訴訟が確定してから死亡した。Aの第一順位の相続人である妻と子は、3ヶ月以内に相続放棄の申述を行い受理されたため、第三順位の相続人である兄弟6名が相続人となった。(直系尊属は既に死亡)
Aの兄弟の一人である被相続人Bは、妻と子の相続放棄の翌月に、自己がAの相続人となったことも知らず、ましてAからの相続放棄の申述をすることなく死亡した。Bの相続人である妻と子Xは、Bの死亡日にBの相続人となったことを知った。
Xは、Bの相続開始後3年後の平成27年11月11日に、G銀行から債権譲渡されたYから確定判決に基づく執行分の送達を受けてから、BがAの相続人であり、XがBからAの相続人としての地位を承継していることを知った。(債務額250万)Xは、平成28年2月5日に相続放棄の申述を行い受理され、Xは、Yに対して強制執行を許さないことを求める執行分付与の異議申立訴訟を提起し、相続放棄の申述が熟慮期間内になされた有効ものかを争点に、最高裁まで争われた。
5.2最高裁の判断
- 民法916条の趣旨は、乙が甲からの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときには、乙から甲の相続人としての地位を承継することを丙が認識した時を熟慮期間の起算点とすることで、甲からの相続について承認又は放棄を選択する機会を丙に保障することにある。
- 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時をいう。
- 再転相続人のXは、平成27年11月11日の執行文の送達により,BからAの相続人としての地位を自己が承継した事実を知ったので,Aからの相続に係る被上告人の熟慮期間は,送達の時から起算され、平成28年2月5日に申述された相続放棄は,熟慮期間内にされたもので有効。
- 再転相続人である丙が、乙の甲に対する相続人としての地位を承継した事実を知った時を起算日とする判例であり、あくまで、丙の認識を基準としています。
尚、被相続人の死亡前に、兄弟姉妹や子などの相続人が死亡していた場合は、甥・姪や孫などは代襲相続人とされますので、再転相続にはならず、民法915条が適用されます。
6.まとめ
熟慮期間の起算日について、債務等の相続財産を認識した時等の例外を認める事情について、リーディングケースとなっている昭和59年の最高裁判例では、「相続財産がまったくないと信じた場合でそう信じたことに過失がないこと」です。
しかし、相続申述受理審判では、遺言や相続人間の協議(暗黙も含む)や慣習等で「自分が取得すべき相続財産が存在しないと信じた場合」まで例外適用を拡張しているようにも見えます。
「自分が取得すべき相続財産が存在しないと信じた場合」でも、「相続財産の調査も相続放棄の申述も期待できない」場合が殆どなので、「相続財産がまったくないと信じた場合」と同じではないかという指摘もあります。
相続放棄申述の受理審判において、家裁は一応の審理で足り、明白な要件の欠缺がない限り原則受理すべきとの所謂原則受理説の見解を明言する裁判例もあります。(3.1.1、3.1,2、3.1.3)
しかし、債権者から提起される訴訟では、受理審判に既判力はなく、より詳細な事情・事実が認定されて無効とされる可能性があります。被相続人がかなりの債務を負っていることが予想される事例では、予防的に相続放棄申述を3ヶ月以内に行うことを強くお勧めします。特に、自分は相続分はいらないというケースでは、絶対に相続放棄申述を行うべきでしょう。
再転相続人の場合は、自己が相続人になったことを知った時、債務の存在を知った時から熟慮期間が起算されます。
(参考論考:河野泰義「判例研究 相続放棄申述の熟慮期間の起算日について判断した事例」)