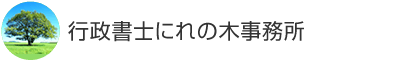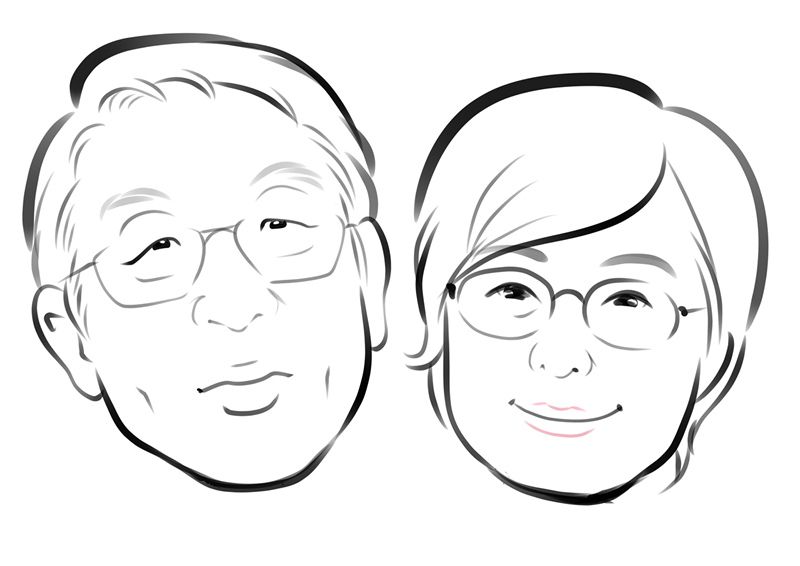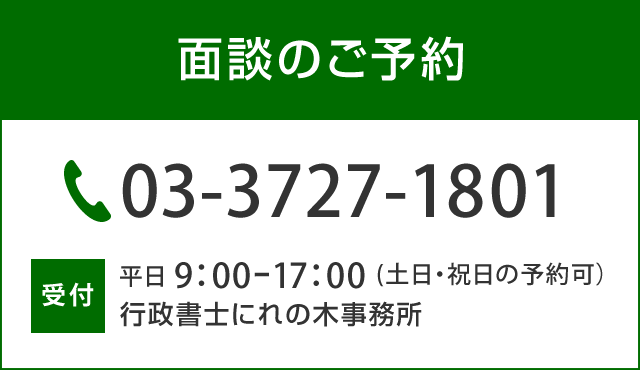目次
離婚時に家をどう処分するか、住まいを確保するかは、財産分与の中で一番大きく深刻な問題です。

家・住居は、夫婦共有財産の中で、金額面から最大の比重をもつ上に、離婚後に、家族がどこに住むかの「住」の問題、住宅ローン債務等多くの複雑な問題を含むので、双方とも譲歩しにくく、離婚協議中で、最も揉める問題の一つです。特に、熟年夫婦の場合はより深刻になるでようです。
「夫名義の家に対する妻の権利は?」という疑問は、殆どの夫婦がもっています。住宅ローンで購入している住居は、99%共有財産です。親からの贈与などで頭金を出している場合等は、共有財産と特有財産が混ざり合っていて、特有財産を共有財産から切り分ける評価が必要です。「2.特有財産と共有財産で購入した住居の評価」で詳述します。
又、夫名義の家だからと言って、家から強制退去を求められる理由はありません。共有財産である場合は当然に、特有財産であっても、殆どの場合、離婚成立前は強制退去や立退きを迫られることはありません。離婚後の場合は、離婚前程は簡単ではなく、各種の問題があり詳細な検討が必要です。
更に、住居が、夫名義だとか、オーバーローンであるからと言って、離婚後は住み続けられないということではありません。協議次第で、婚姻住宅に継続居住する事は十分に可能で、多様な選択肢があります。
離婚後に二世帯住宅を処分する時は、土地の使用借権を評価して解決すべきです。離婚後に契約者でない妻が賃貸住宅に住み続けても、無断譲渡で契約が解除されないというのが判例です。公営住宅は、条例次第ですが、離婚時の契約承継を認める自治体が多いようです。
1.夫名義の家・妻の権利
婚姻中に、家の購入時に組んだ住宅ローンの返済を行っている場合は、まず間違いなく、夫名義の家は共有財産で、妻は夫に対して2分の1の共有権をもっています。
不動産登記名義が夫婦共有名義である場合はもちろん、夫単独名義で、かつ住宅ローンの債務者名義が夫でも、共有財産です。
登記上の所有権名義や、住宅ローンの債務者名義がどうなっているかは、夫婦間では、全く関係ありません。
1.1婚姻後の職業収入で購入
婚姻後に住宅ローンを組んで、住居を購入し、婚姻後の夫の職業収入でローン返済を行っている場合は、夫婦間では住居は共有財産となり、離婚時の財産分与の対象となります。
妻が専業主婦で職業収入が全くなくても、家事労働を通じた協力扶助の結果、共有財産が形成されたものと見て、専業主婦にも2分の1の寄与割合が認められます。夫名義の給与振込口座からローン返済額が引き落とされる場合が多いと思いますが、夫婦間では、専業主婦も2分の1の返済を行っていると見做されます。
婚姻後の職業収入を原資として頭金が支払われた場合、夫婦の住居に対する寄与割合はそれぞれ2分の1になります。しかし、夫婦いづれかの特有財産から頭金や期前返済金等に充てられた場合は、住居全体の寄与割合は2分の1づつとはなりません。2を参照して下さい。
1.2夫が婚姻前に購入
婚姻前に購入してローンも完済しているなら夫の特有財産ですが、婚姻後も、住宅ローンの返済が継続した場合は共有財産です。
婚姻前のローン返済額などは、夫の特有財産になるので、住居全体の寄与割合は、頭金等に特有財産を充当した場合と同じく、2分の1づつとはなりません。
1.3相続不動産
夫婦の何れかが、相続で取得した不動産(移転登記の原因が「相続」と記載)か、相続で得た現金で購入した住居は、特有財産で、財産分与の対象から外れます。
一方の特有財産であっても、夫婦には同居義務・協力扶助義務(民752条)があるので、婚姻が継続する限り、他方の配偶者には住居の使用権があり、明渡しや強制退去を求められることはありません。詳しくは、「4.離婚後、妻は夫単独名義の家に住めないか?」をよくお読み下さい。
2.特有財産(頭金)と共有財産(住宅ローン)で購入した住居の評価
実家からの贈与金や婚姻前の預金を頭金に充てた住居は、特有財産と共有財産が混じり合った財産になるので、頭金等をどう評価して、夫婦間でどう分けるかは、とても難しい問題です。

完璧な評価法はありませんが、理屈の整った二つの評価法を例題に基づいて具体的に説明します。
2.1ローン付住居の評価
「純資産額=時価―住宅ローン残高」が財産分与対象となります。
2.2頭金は特有財産か?
どちらかの親(妻の親が贈与したと仮定)が頭金を贈与した時、その性格が問題となります。
贈与当時は、夫婦双方への贈与の性格だったと思いますが、「円満な婚姻が継続する限り」という黙示の条件付だったと考え、妻の特有財産として扱われることが多いようです。(人事訴訟の実務」松原正明編 新日本法規 P341)
2.3頭金等の特有財産とローンで購入した住居の評価法
夫婦各自の頭金等の特有財産と住宅ローン返済による共有財産の評価法について、裁判官が離婚訴訟などで使っている二つの評価法(A・B)を紹介します。完璧な正解は全くありません。要は当事者が了解すればどの方法でも可能です。下記に紹介する二つの方法は、ロジックにも破綻がなく、比較的理解しやすい方法だと思います。この二つ以外の評価方法も当然にあるでしょう。
例題
(万円)
| 不動産購入価格 | 5000 | |
|---|---|---|
| 頭金・親贈与 | 夫 | 700 |
| 妻 | 300 | |
| 住宅ローン | 借入 | 4000 |
| 住宅ローン | 返済 | 1000 |
| 住宅ローン | 残高 | 3000 |
| 不動産時価 | 基準 | 4000 |
| 純資産額 =時価―ローン残 |
基準 | 1000 |
基準:基準時、別居時又は離婚時
評価法A
| 現役裁判官(離婚訴訟等の人事訴訟担当)による調停委員向講義(筆者受講)や元裁判官の著書(「改訂版 離婚調停・離婚訴訟」(岡健太郎他 青林書院P176)で例示された評価方法。評価法Bに比べて、頭金等特有財産の評価が高くなる傾向。 |
- 特有財産・評価額
-
夫 頭金700×時価4000/買価5000
(時価4000×頭金700/買価5000)560 妻 頭金300×時価4000/買価5000
(時価4000×頭金700/買価5000)240 - 共有財産=住宅ローン返済
-
計 純資産1000―夫頭金560―妻頭金240
(ローン4000×時価4000/買価5000―ローン残3000)200 - 夫婦の取得額
-
夫 特有財産560 + 共有財産200 × 1/2 660 妻 特有財産240 + 共有財産200 × 1/2 340
評価法B
| 裁判官の著書(「人事訴訟の実務」松原正明編 新日本法規 P342-343)で示されている評価法で、頭金もローン返済額も同じ投下資本と見做して、夫婦の寄与した投下資本額の比率で純資産額を按分して評価する方法。評価法Aに比して、特有財産の評価が低くなる傾向。返済額を元本ではなく、元利合計額とすると、より特有財産の評価が下がる。 |
- 投下資本額・寄与額
-
夫 特有財産700+元本返済1000×1/2 1200 妻 特有財産300+元本返済1000×1/2 800 計 夫頭金700+妻頭金300+元本返済1000 2000 - 夫婦の取得額
-
夫 純資産1000×夫寄与額1200/寄与額計2000 600 妻 純資産1000×妻寄与額800/寄与額計2000 400
まとめ
|
2.4頭金支出額100%を返してほしい?
まず頭金等の特有財産支出額を100%返してほしいと主張する当事者も多いです。
いずれの評価法を採用しても、頭金等の流動資産は、既に不動産という固定資産に転化・化体しているので、当初支出の頭金等の価値は、固定資産の時価にあわせて変動せざるを得ないので、相当性を欠く主張だと思います。
時価が購入時より上昇している場合は、頭金等の特有財産の部分は、当初支出額より高く評価され、高い評価に見合う財源もありますが、時価が購入時より下落している場合は、頭金100%を保証する原資がないので、他方当事者にとって酷な主張となります。いずれの場合でも、時価で評価するべきだと思います。
2.5別居後のローン返済等
別居後の元本返済は返済当事者の特有財産になります。上記に示した評価法の算式を応用して計算できます。
2.6特有財産による中途返済
相続財産等で期前返済した場合も、期前返済額が特有財産になります。4)と同様に評価額を計算できます。
2.7評価法あれこれ
元裁判官が書いている書籍(かなり売れている?)は、評価法Aにおける頭金等の特有財産の評価法を、純資産額×(特有財産/購入額)としています。(ローン返済額の評価は、純資産×(当初ローン借入額/購入額)となる。)
ローンが完済されたと当初から仮定して、購入時の資金調達比率で純資産額を按分しています。住宅ローンの完済時期が近い場合を除き、相当ではない方法だと思います。(現役裁判官からも当時から批判があるようです。今は修正されているかも知れませんが…。)
3.離婚前、妻は夫名義の家からの強制退去・明渡請求や売却を拒否できる
多くの夫は、ローン返済を行う自分単独名義の家について、「俺の家」だから、売るのも妻を退去させるのも自由にできると思っているようです。多くの場合、共有財産ですから、妻を追い出したりするようなことはできません。相続等で得た特有財産である住居でも、殆どの場合、婚姻している限りは妻に明渡し求めることは認められません。
共有権の仕組み等から家の売却や妻の追い出しの問題点を説明し、裁判例の考え方について紹介します。
3.1住居(居住不動産)が共有財産の場合は、強制退去・明渡請求は不可能
居住不動産が夫単独名義でも、夫婦間では共有財産である場合が大半であることは、上記「1.夫名義の家・妻の権利」で詳しく説明しています。登記が共有名義(妻の持分がほんの少しでも)である場合は当然に、夫単独名義の場合でも夫婦間(当事者間)では大半が共有財産なので、妻は共有権者として居住不動産に正当に居住する権限をもちます。夫は、自分の単独名義であることを理由に、離婚前に住居の明渡・強制退去を請求できません。
不動産登記制度は、不動産における物権・権利の「第三者」に対する公示方法です。第三者に向けて所有権等の物権や権利を対抗する(=自分の権利を主張すること)要件で、不動産に関して第三者との法律関係を規律します。しかし、夫婦のような当事者間で所有権等を主張するのに登記は不要です。妻名義の登記がなくても、妻は夫に対して、以下のような事情があれば、当然に共有権を主張できます。
夫が各月自己の給与口座等から自分名義の住宅ローンの返済を履行している場合は、共有財産である夫の職業収入(夫婦の生活費)からローンを返済してので、ローン返済により、各月毎に夫婦共有財産が形成され増加します。
上記の事実を妻は当然に熟知し、夫も妻が知っていることを了知しているので、妻は夫にとって第三者ではなく当事者です。従い、登記なしに、妻は夫に対してだけは不動産に対する共有権を主張できます。(第三者に対しては主張できません。)
登記の専門家である司法書士の調停委員が、第三者関係と当事者関係の法律関係の差異を理解できず、妻は、登記なしには夫に共有権を対抗できないと言った事に驚愕したことがあります。法理解の基本が理解できず悲しく惨めなことです。
共有者は、持分権の多寡に関係なく、共有物全体の使用収益権をもっているので、他の共有者は、正当な権限をもって共有物を占有する共有者に対して、共有物の明渡を求めることはできないという判例が確立しています。(最一小判昭和41.5.19 判例タイムズ193号P91)
占有する共有者は、他の共有者の持分権を侵害しているが、持分権の侵害を理由に、正当な権限をもつ占有者に明渡請求はできないというのが判旨です。
従い、登記上の単独所有権者である夫でも、夫婦間では共有財産である居住不動産を占有する妻に対して明渡請求を求めて、強制退去させることはできません。
3.2離婚前、夫による住居の売却は、通常は、阻止できる
夫が100%の所有権名義をもつ住居であれば、夫だけの意思で、第三者と売買契約を締結することは、法的には可能です。(例え僅かでも、妻に共有持分があれば、売買契約は共有者全員で締結の必要があり、妻の意思に反して売買契約を締結できません。民251条)。
しかし、夫が第三者と売買契約を締結したとしても、住居が共有財産である限り、前述したように夫から妻に対する強制退去・明渡請求が認容されず、結果的に不動産の引渡しが不能となるので、最終的に売買契約の履行はできません。夫が相続等で取得した特有財産であったとしても、次の3)に述べるように、殆どの場合で、強制退去・明渡請求はできません。
住居の買受人は、不動産の引渡を受けられない時点で、通常は解約金(手付金の2倍)を要求して売買契約を解約します。(解約しないで、登記を買受人に移転して、妻の住居の明渡を求めてきた場合は、住居から退去せざるを得ませんが、めったにないケースでしょう。)売却阻止のポイントは、どんな脅かしにあったとしても、住居から引越しないことです。
上のようなマレな場合にも備えて、売買契約前の買受人の内見に協力せずに、売買契約が締結されないようにして下さい。購入希望者の内見は、夫に対する妻の共有持分権や使用借権等に基づいて当然に拒絶できます。購入希望者や不動産仲介業者は、妻との関係で、いかなる契約関係や権利を有しません。
事件屋的な不動産会社が、名義上の所有者である夫から、内見で不動産の現況もチェックせずに、市価から相当値引きさせて購入して後、不動産会社が妻に明渡を迫る場合も、希にはあるようです。不動産会社は、妻にとっては第三者となるので、不動産会社からの明渡・立退き請求を妻は拒めなくなります。夫が別居するようなそぶりを見せた時から、弁護士等に相談すべきでしょう。早いタイミングで、自分自身を法的に護るあらゆる方策を勉強すべきです。
上記のような場合に備えて、離婚調停を申立てて、同時に居住不動産の保全申立てをして、夫が売却不可能にすること等を弁護士にやってもらうべきです。
3.3住居が特有財産の場合でも、強制退去・明渡請求できない場合が殆ど
離婚前は、家が配偶者の特有財産であっても、配偶者に別居の有責性等がない限りは他の配偶者の強制退去や明渡請求は認容されません。
有責配偶者からの明渡・強制退去請求
有責配偶者の夫(他の女性との間で子をもうけ、女性及び子と同居するために自宅を出て別居)が、婚姻が破綻しているので同居義務もなくなったとして、相続で取得した自宅不動産に居住する妻に明渡請求を求めました。判決は、同居義務及び協力・扶助義務(民752条)を負う妻に対して、婚姻中に長期間同居してきた自宅を一方的に明渡請求することは、権利の濫用であるとして明渡請求を否認。(東京地判平成25.2.28)
無責配偶者からの明渡・強制退去請求
客観的に婚姻が破綻しているだけでは、夫婦の同居義務に基づく占有権原は消滅しません。婚姻関係が解消して、始めて明渡請求ができる。
占有配偶者側に、不貞・暴力行為等婚姻関係の破綻に関する有責性が認められる場合に、同居義務に基づく占有権原の主張が逆に権利濫用と評価され、強制退去・明渡請求が認められるような裁判例の傾向となっているようです。(東京地判平成24.2.9、東京地判平成3.3.6判例タイムズ768号P224他)
まとめ
|
出典:論考「婚姻関係破綻後の自宅不動産の明渡請求について」(弁護士 茶木真理子、Oike Library No.40 2014/10 )
4.離婚後、妻は夫単独名義の家に住めないか?
妻側が、離婚後も子供の学校等のことから、「夫名義の婚姻時の住居」に住み続けたいと希望する場合も相当あります。ここでは、離婚後に婚姻住居に継続して住む場合の法的な枠組を説明します。具体的方法は下記を参照して下さい。
4.1離婚後は他人で第三者関係
離婚前に財産分与の協議もせず、かつ離婚後2年以内に財産分与の請求も行わないで、夫名義の家に住むのは、他人の家に住むことと同じです。 元夫は第三者と同じ立場になるので、元夫からの住居の強制退去・明渡請求は認容される可能性は大きいです。
但し、離婚後でも登記なしに共有財産であることを認め、元夫の立退き、明渡請求を否認した裁判例があります。(東京地判平成24.12.27 判例時報2179号P78)
事案の概要
元妻が離婚訴訟を提起し、付帯処分として財産分与を求めて、離婚が高裁で確定。1審・2審共、夫単独名義の住居については、オーバーローンで財産分与対象とならないとして何も命じず、預金の分割のみ命じた。(結果的に不動産の登記名義は、離婚前の夫単独のままに放置された。)元妻は、住居に住み続けたため、元夫は所有権に基づく明渡請求を求めた。
判旨
元妻は頭金に特有財産も投じている共有財産であるのに、オーバーローンであるという理由からたまたま登記名義を有していた元夫の単独所有になるのは、極めて不公平。離婚訴訟の担当裁判所は、離婚時の財産分与とは別に、不動産の共有関係について審理判断すべきであった。
元妻の住居に対する1/3の共有持分権を認定して、明渡請求は棄却。
但し、元妻は、不動産を占有して夫の持分権を侵害しているとして、賃料相場の2/3に相当する損害賠償を命じた。
判例の考察
この事案は、オーバーローンであっても妻の共有持分があると認めて明渡請求を否認した点で注目されます。オーバーローンであることと共有持分は全く関係ないことなので、当然な判決とも言えます。しかし、本件は、元妻が離婚前から婚姻住居をも含む財産分与を求めていたケースであり、財産分与請求について何らの意思表示をしない者が、離婚後に夫単独名義の住居の強制退去・明渡請求を拒む確実な論拠にはならないように思われます。
4.2元夫単独名義の家に、元妻が居住継続する為に
財産分与請求の意思表示
できるだけ離婚前に、離婚後でも、できるだけ早く(2年が過ぎると時効―除斥期間終了)、内容証明郵便で住居を含む財産分与請求の意思表示を行う。
共有財産である婚姻住居の処分も、財産分与全体も未了なので、元夫の関係では、登記なしに住居の共有持分を主張でき、元夫の強制退去・明渡請求は否認されるでしょう。
当事者(元夫・元妻)間での共有持分の確認
離婚後は、住宅ローンを債務者の夫が引受けて完済する前提でも、妻の共有持分は僅かでもかならずあります。これを当事者間の書面(できるだけ公正証書)で確認さえすれば、元夫は、元妻に対して、婚姻住居からの強制退去・明渡を求められないし、元夫は住居を有効に売却できません。但し、夫の持分権の侵害の問題は生じます。
共有持分の計算例
例題2.3での評価法Bに準拠して計算例を示します。住宅ローンは、名義者の夫が返済継続する。何もしなければ、自動的に名義者が債務引受して継続返済することとなります。
|
上記は妻の特有財産の頭金が300万円ある場合ですが、元妻の特有財産がゼロでローン返済からの共有財産のみとした場合でも、共有持分は11%になります。絶対にゼロにはなりません。
当事者間での賃貸借契約締結
元夫の持分権の侵害となって損害賠償請求を受けないように、賃料を賃料相場×元夫の持分相当とする賃貸借契約を書面で締結すべきでしょう。
当事者間の共有持分権に加えて、借地借家法が適用されて、賃借人として保護されるので、住居を安定的に使用できます。
賃貸期間は、借地借家法上は、上限はなく、長期間の賃貸借契約を元夫と元妻間で締結すれば、長期間安定的に使用できます。
5.オーバーローンと不動産分与
持家がオーバーローンの場合は、財産分与上の評価をゼロとするのが通常です。しかし、オーバーローンであっても、夫婦それぞれの共有持分はあります。ローン債務者の夫が今後とも債務を返済することを前提とした共有持分の計算方法を紹介します。

5.1財産分与額はゼロとするのが通常
居住不動産の時価が住宅ローン残高を下廻る場合(オーバーローン)は、財産分与額はゼロにするのが、実務の主流です。ゼロを財産分与額の下限とします。
もちろん、預貯金等他の資産と合算してプラスとなれば、そのプラス額が財産分与対象となります。
5.2オーバーローンでも夫婦の共有持分権あり
オーバーローンだという理由で何もしなければ、離婚後、居住不動産は、たまたま所有権の登記名義者であった者(たとえば夫)に帰属し、他方当事者(妻)は、無権利者となって、住居の使用もできなくなり、強制退去・明渡を求められた場合、対抗する手段はありません。
4.2で詳述したように、ローンで購入した住居の場合は、離婚時に妻に必ず何らかの共有持分があります。夫がローンの名義者で残債を引受ける場合、妻の共有持分がかなり小さくなるでしょうが、ゼロになることはありません。
オーバーローンであるからと言って、妻の離婚時の共有持分がゼロにはなりません。4.1で詳述したように、オーバーローン時に、登記なしに元妻の共有持分を認めて、元夫の立退き・明渡請求を否認した判例があります。(東京地判平成24.12.27 判例時報2179号P78)
5.3共有持分権の確認方法
オーバーローンの有無と妻の共有持分は全く無関係です。共有持分は、夫婦の不動産形成の寄与割合そのものなので、オーバーローンの有無とは関係ありません
しかし、元妻が元夫との間で共有持分の権利を主張するためには、離婚協議書や離婚給付等契約公正証書等に、元夫婦間における共有持分を確認する条項を入れる必要があります。この確認条項で、元妻が元夫との間で無権利者とならずに住居からの強制退去や明渡を求められることに対する対抗策となります。
更に、不動産がオーバーローンの状況は永久ではありません。少なくとも住宅ローンを完済した時点では純資産額はプラスに転化する場合が殆どでしょう。その時に、本来何らかの共有持分をもつ元妻が何も得られないというのは不公平です。元夫婦間の共有持分を離婚時に確認しておけば、将来純資産がプラスとなった場合、プラス額に対する共有持分相当額を元妻が得られます。
5.4共有持分権の登記
共有持分を離婚後に正式登記するには、住宅ローンの債権者(銀行などの金融機関)の合意が必要な場合が殆どです。通常は、融資契約書には合意なしに担保不動産の現状を変更した場合、期限の利益を喪失する[=一括期前返済を求められる]と規定されている場合が殆どです。
共有登記に金融機関等の同意が得られない場合は、少なくとも、当事者間で共有持分を文書で確認すべきですし、共有持分の仮登記も検討すべきでしょう。当事者間で共有持分を確認すれば、登記なしに、元夫には共有権を主張できます。ローン完済を条件とする仮登記は、第三者対抗力はありませんが、仮登記のついた不動産の売買は、仮登記権利者を巻き込んだ売買となるので、売却時には、担保権の抹消を行うために、必ず住居の売却の事実を知ることができます。残債の弁済後に剰余金が残れば、当然に共有持分相当額の支払を求めます。
6.財産分与と婚姻住居の確保
財産分与を登記原因として、妻が婚姻中の住居を単独名義で取得したり、賃貸借契約や使用貸借契約を締結して、離婚後も住み続ける場合も多く見受けられます。住宅ローンの債務引受の問題、離婚後は完全な他人になる問題など困難な事項を克服する必要があります。問妻が住居を確保することを前提に、問題を解決して住居を安定的に確保する方法を説明します。
6.1離婚後に第三者対抗力のある所有権移転登記
離婚と同時に、居住不動産の相手方持分の補償である代償金を、現金、延払い、慰謝料等他債権との相殺等の手段で支払い、住居取得者による相手方住宅ローンの免責的債務引受や住居取得者自身による借換や残債一括返済等により相手方名義の住宅ローンを消滅させてます。その後に 財産分与を登記原因とする第三者対抗力のある移転登記を行います。
2.3例題における支払額(評価法A準拠)
- 夫持分権の買取・代償金
夫・持分権評価額: 660万(特有財産・頭金560+共有財産100) - 妻による夫・住宅ローンの免責的債務引受(又は、借換え、一括返済等):3000万
- 公平さの検証
| 妻・離婚時に取得する総資産(家の時価)(1) | 4000 |
|---|---|
| 妻・ローン債務引受 (2) | -3000 |
| 妻→夫 代償金 (3) | -660 |
| 離婚時・妻取得純資産額 (1)+(2)+(3) | 340 |
| 妻・持分権評価(2.3例題) | 340 |
6.2住宅ローン完済後に所有権移転登記
妻が住宅ローンの免責的債務引受等により夫の住宅ローンを消滅させることができない場合は、離婚後も夫が住宅ローンを返済し、妻が履行引受(夫・返済原資を妻から夫に各月支払)する場合や、妻が履行引受も行わない場合など、各種のヴァリエーションがあります
離婚時点での夫から妻への移転登記に金融機関等の同意が得られない場合、妻への所有権移転登記は、夫の債務完済後にするとの条項を公正証書に付記し、夫が第三者に売却してしまうよう場合に備えて、登記順位保全のために妻が仮登記を行うように促すのが公証人の実務です。(「新版証書の作成と文例―全訂家事関係編―」(日本公証人連合会P49、立花書房)
6.3賃貸借契約
元夫婦間で賃貸借契約を締結して、妻等は、借地借家法上の保護を受ける。
元夫が住宅ローン債務を遅滞なく履行することがポイントとなりますが、ローン返済できる資力はあるのに、ローン返済をしない人は極めてマレです。債務不履行があると、信用情報上、ブラックリストに載って、クレジットカードの取り消し等普通の社会生活が送れなくなります。
6.4使用貸借契約
無償で賃料の支払がない場合は、使用貸借契約と言います。実務では、明渡時期を明確にした上で、離婚調停ではかなり行われています。
賃貸借と異なり、借地借家法の保護を受けられず、元夫が住居を売却した場合、住居の買受人に対抗できません。(もちろん、元夫は元妻に対する重大な債務不履行で損害賠償する必要はあります。)一定程度の元夫への信頼感が必要でしょう。事情によっては、「権利の濫用」であるとして明渡請求を認めなかったり、立退き料の支払が命じられる場合もあるかも知れません。
7.二世帯住宅と離婚
妻か夫の実家の敷地に夫が住宅ローンを調達して2世帯住宅を建設した後に夫婦が離婚することは、マレではないようです。(調停委員としてそういうケースを複数担当したこともあります。)
土地に比較して建物の評価が異常に低い日本において、建物だけを夫婦共有財産とすると、財産分与対象額は相当に低くなります。
土地の使用借権として、更地価格の10~20%を加えるのが裁判実務で、協議離婚の場合でもそうすべきです。
7.1離婚後の二世帯住宅の処分
夫婦いずれかの父母所有の敷地上に、二世帯住宅又は夫婦単独の住居を夫の住宅ローン等で建設したと仮定します。
建物は、共有財産ですが、第三者に販売したくない・できない場合が殆どでしょう。
共有持分の評価額を支払って、どちらかの単独所有とするしかない場合が大半です。
7.2土地所有権のない不動産の評価
建物は減価償却資産なので、不動産としての価値が減価(特に日本では)して、20年近く程度経過すると無価値とされることも少ないないでしょう。
建物の評価は、一応、固定資産税評価額等を使用せざるを得ないようです。
所有権はなくても、夫婦は、土地の使用貸借権はあります。訴訟の場合は、土地の使用借権の評価を建物の評価に加えて財産分与対象とするのが一般的です。
協議離婚の場合でも土地の使用借権を子の夫婦世帯の不動産の価値に含めるのが公平だと思います。
土地の使用借権は、下記のように評価されます。(「遺産分割事件の処理をめぐる諸問題」司法研修所編 法曹会刊P309-310)
・非堅固建物の場合(木造等):更地価格の10~20%
・堅固建物の場合(コンクリート造等):更地価格の10~30%
7.3例題
前提
| 建物床面積 | 夫婦世帯 | 100㎡ |
|---|---|---|
| 親世帯 | 120㎡ | |
| 敷地時価 | 1億2000万円 | |
| 特有財産 | なし | |
共有財産の夫婦各持分の評価
(万円)
| 建物評価 | 固定資産税評価 | 300 |
|---|---|---|
| 土地使用借権評価 | 1億2,000×100㎡/(100㎡+110㎡)×15% | 860 |
| 夫婦住居評価 | 建物300+土地使用借権860 | 1160 |
| 夫婦持分 | 1,160×1/2 | 580 |
8.賃貸住居と離婚
賃貸住宅に居住していて離婚する場合には、賃貸借契約の譲渡性が問題になります。夫名義の賃貸契約なので契約の名義変更をあきらめる元妻も多いようですが、離婚後に元妻が賃貸借契約の譲渡を当然に受けられるというのが裁判例です。但し、公営住宅の場合は、各自治体の条例次第なのでよく調べて下さい。
8.1賃貸借契約の譲渡
離婚後、夫が契約していた賃貸住居を妻が住み続けることは、形式的には、賃貸借契約の譲渡(民612条)になり、家主は賃貸借契約を解除できるように見えます。(同条第2項)
しかし、本来は、妻である限りそのまま居住を継続し得た筈であり、夫から妻への賃借権の譲渡は、家主が契約解除できる程の背信性がないとして、夫から妻への契約譲渡を認容するのが、近時の確立した判例です。
上記にいう妻の中には、事実婚(内縁関係)による妻も含みます。
離婚や事実婚の解消が決まったら、協議書等で賃借権の譲渡を確認すると共に、家主に対して妻への賃貸借契約譲渡の手続をすべきで、黙って住み続けるのは避けるべきです。
8.2公営住宅の場合
公営住宅は、家賃が低廉であることから入居希望者が多く、公募による入居が原則となっていることから、原則、賃借権の譲渡が禁止されています。(公営住宅法27条2項)
東京都・神奈川県の場合は、条例で、契約者の死亡・離婚の場合だけ、原則配偶者への譲渡が認められています。配偶者には、事実婚も含むと思いますが、詳しくは、各自治体の相談窓口に問い合わせて下さい。
8.3別居中の賃貸借契約解除
契約者である限り、夫は契約解除は合法的に行えます。
しかし、未だ婚姻中であることから、当然に離婚と同等かそれ以上に、妻の居住権は保護されるのが判例ですが、妻が賃料を支払続けることが前提となります。(東京地判昭39・8・5判タ168号165頁、京都地判昭54・3・27判タ384号94頁など)
賃料を払えない場合は、家庭裁判所での婚姻費用分担の調停・審判申立てを考慮すべきです。
直ちに家主と協議して、新契約の締結か、夫の契約条件は引き継いだまま名義だけ変更する等の手続をとるべきでしょう。