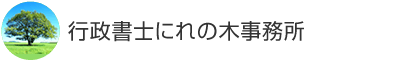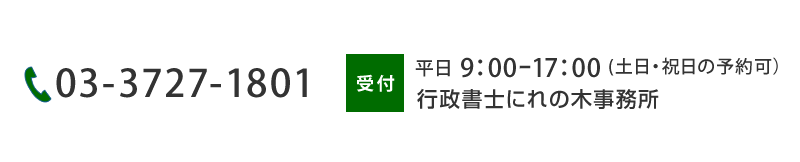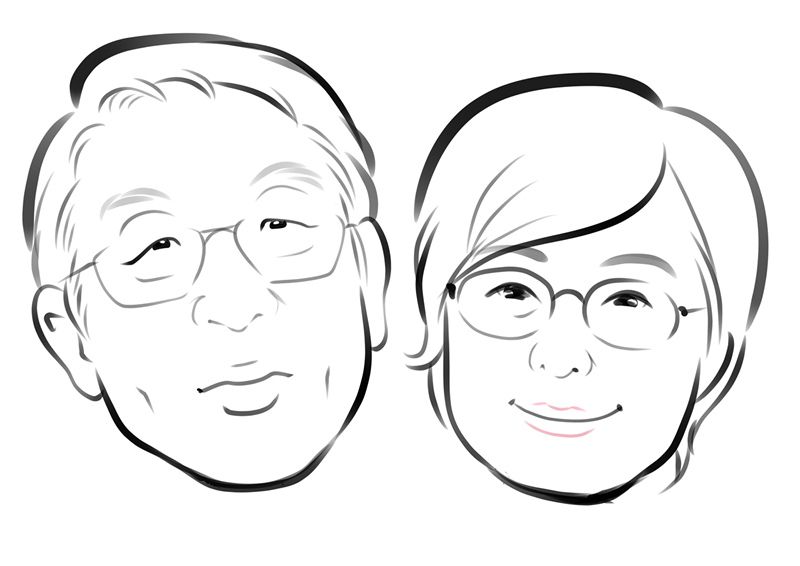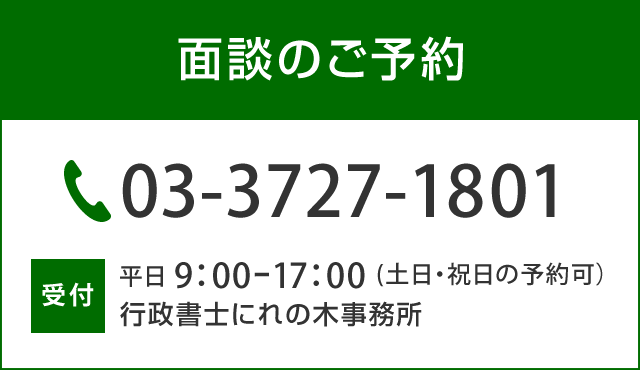目次
離婚時に、夫から自分の子ではないから養育費を払わないと言われる場合があります。婚姻後200日以内の場合等、子の出生時期によっては、嫡出推定が働かない場合があるので、慎重に対処すべきです。
永らく別居中で、離婚後300日以内に出生した子は、前夫の子だと嫡出推定されます。他の男性の子であると主張したい場合は、親子関係不存在という277条審判を家庭裁判所に申立てる必要があります。

未成年の養子縁組には、原則、家庭裁判所の許可が必要です。但し、再婚相手の養子とする場合は、届出だけで済みます。再婚相手と離婚する場合は、養子縁組している子と養親との離縁をしなければ、養親の親権が継続します。養子縁組と婚姻は、別々の身分関係で二つの身分関係があります。
相続税対策で養子縁組を結ぶ場合も見受けられますが、税法上は、現在は、一人の養子しか基礎控除対象になりません。
1.親子の血縁関係
1.1離婚の時に、自分の子でないと言われ、養育費の支払いを拒否された?
子もが出生した状況によっては、嫡出推定(母と婚姻中の夫の子―嫡出子・婚内子―であると法的に推定されること)が働かないで、法的に親子関係が否定される場合があります。慎重に行動して下さい。
いわゆる「できちゃった婚」の場合は、婚姻届受理後、200日以内に誕生した子は、「推定されない嫡出子」とされて、夫は、いつでも、「親子関係不存在確認」の調停(277条審判)や訴訟を起こせます。DNA鑑定等で、血縁関係がないと証明されると親子関係が否定されることもあります。
前夫と事実上の離婚状態にある時に妊娠し、離婚後に子供を出生した場合は、離婚後300日以内に出生した子供は、前夫の嫡出推定が働き、戸籍上は、前夫の子とされます。前夫は、「嫡出否認」の調停・訴訟を起こして、DNA鑑定等を求め、父子関係を自ら否定することも可能です。ただし、子の出生後1年以上経過している場合は、父親には、「嫡出否認」で父子関係を争うことは不可能になります。 (民法777条) 子ども(子の法定代理人としての母も)が、実際の父が戸籍上の父と違うとして「親子関係不存在確認」の調停・訴訟を起こすこともできます。夫との別居など事実上の離婚状態や夫の海外滞在等実質的な妊娠可能性がない事を証明すれば、「推定が及ばない嫡出子」として、父子関係を否定することもできますが、客観的・外観的な事情の内容によります。
2.養子縁組
2.1連れ子養子(実母が再婚と仮定)
原則として、未成年の養子縁組には家裁の許可が必要です。(民法798条)しかし、再婚する配偶者の子と養子縁組する場合、許可は不要で役所の戸籍係への届出のみで養子縁組できます。(民法798条但書)子が15才未満の場合は、親権者である母が代諾権者となるので、養父と母だけで届出ができます。(民法797条1項) 子が15才以上の時は、養父と子が届出の当事者になります。子が母の嫡出子である時は、子と養父との養子縁組だけが必要です。(民法795条但書)
しかし、子が母の非嫡出子(法律婚以外で出生した子ー事実婚での子等)である場合は、夫婦共同縁組を届け出る必要があります。(民法795条)共同縁組とは夫と子との養子縁組と妻と子との養子縁組を同時に届け出る事を言います。夫は養父となり、実母は養母にもなります。実親と実子の養子縁組も、子が非嫡出子である限り認められます。
2.2養子縁組の解消―再婚後の離婚
連れ子再婚して、夫と自分の子が養子縁組して後に、再婚相手と離婚する際の問題です。養父のもつ親権と実親のもつ親権は、形式及び内容とも完全に対等です。子と養父が離縁しない限り、養父は親権をもつので、離婚時には、親権者指定の協議が必要です。まず、子と養父が離縁して親権者協議を不要とすべきでしょう。
夫婦の身分関係と養親子の身分関係は、完全に独立しているので、離婚に先立って、子と養父が離縁することは可能です。子どもが15才未満の時は、母が、子の意思を代理する代諾権者となって、養父と協議します。 離縁が成立したら、前述の親権者協議は不要になります。子が15才以上の場合は、子ども自身が養父との協議離縁の当事者になります。養子縁組を届出る際と同一です。
3.相続税節税目的の養子縁組
相続税の節税のために、子と祖父・祖母の間で養子縁組することはよく見られます。民法上は、養子縁組の数に制限はなく、自由にできます。
しかし、相続税法上は無制限ではありません。法定相続人一人当たりの600万円の基礎控除が適用されるのは、実子がいる場合は、養子は一人だけで、実子はいない場合は二人だけです。更に、孫を養子にする場合は、相続税は2割増になるので、慎重な検討が必要です。