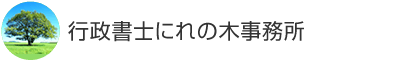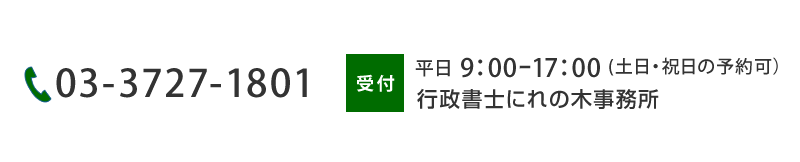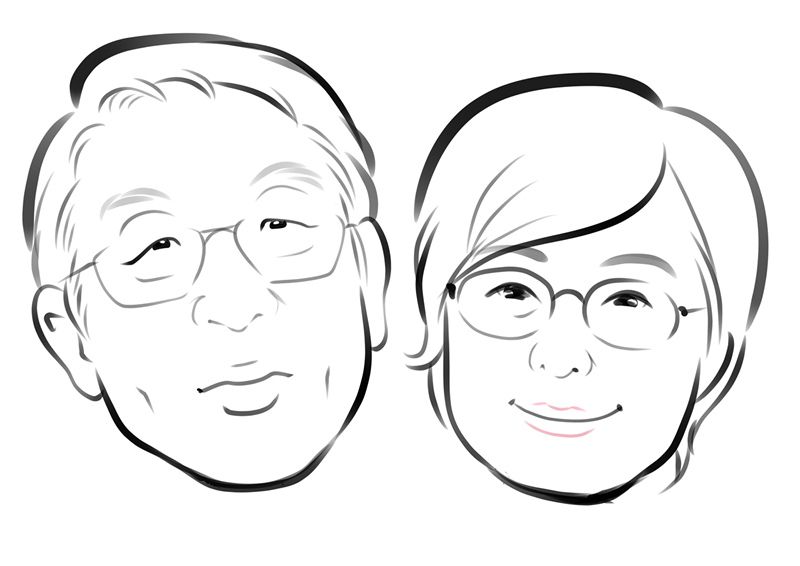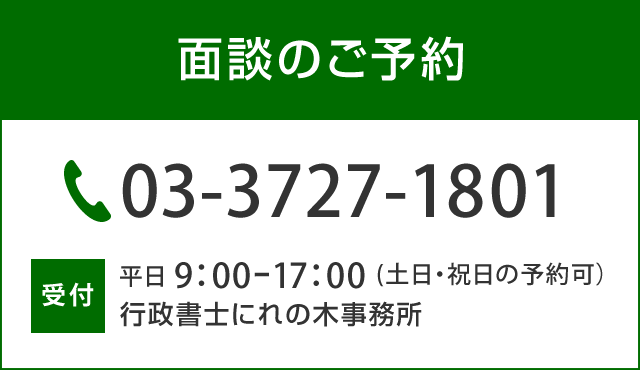家財・家具のように共同生活に使用する財産は、名実ともに共有財産ですが、民法762条1項の文言「婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」からは、夫婦の一方からの収入により取得された一方名義の財産は、特有財産に属するように、一見は、見えます。
しかし、婚姻中の夫婦の有形無形の協力により得られた財産は、購入の原資や名義の如何を問わず、実質的な夫婦共有財産として扱われ、婚姻が解消される時に、公平性の観点から精算する手続が財産分与です。最高裁は、「離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を精算分配するもの」としています。(最高裁判例昭和46年7月23日)
尚、協力には、家事労働など無形のものも含まれるので、専業主婦であって夫の収入によって取得した夫名義の財産も、実質的共有財産です。
実質的共有関係の法的性格は、物権上の共有とする見解もありますが、多数説は、共有権は潜在的なもので、第三者には主張できず、離婚の際に、財産分与によって帰属が決められとしています。
物権上の共有関係を認める説からは、離婚時の夫婦共有財産の解消は、民法256条の共有物分割請求によることも許容することになりますが、判例の大勢や多数説は、財産分与請求によるべきとしています。
- 夫婦の協力で得た収入で取得した一方名義の財産は共有財産(裁判例)
- 別居中の夫名義預金(共有財産)引出しに違法性はないー裁判例
- 財産分与の合意がない限り、共有持分権に基づく不当利得は問えないー裁判例
- 離婚と財産分与ー共有財産の判別、分与額の計算方法、税等を解説
- 離婚と住居-家の処分、住まいの確保、頭金・ローンの処置問題を解説
- 内縁関係解消時には財産分与が適用されても、死亡時には適用されない
- 財産分与請求権は、離婚後に請求して始めて発生し、相続の対象に

実質的共有・夫婦共有財産の法的性格
以下2説あるが、潜在説が多数説。
- 物権的共有説:少数説
実質的共有を民法249条以下の共有と同一と考えて、共有物分割請求も可能とする。 - 潜在説・内部説:多数説
第三者との関係では、実質的共有は主張できず、共有関係は、離婚時に、財産分与によって最終的に帰属が決せられる。共有物分割請求は否定する。共有持分を無形の寄与・協力も含めて判断する実務から、潜在的共有とせざるを得ないとの考え方である。
他方、寄与を有形・経済的寄与を主として判断するのであれば、物権上の持分まで肯定できる余地はあるとの意見あり。
離婚前における共有財産としての主張の当否
実質的共有を、物権的な共有と考えるのあれば、婚姻中、離婚後を問わず、共有物分割請求できることとなるが、潜在的共有と考える多数説では、持分に基づく、持分確認、持分移転登記手続請求、共有物分割請求は認められないとする。
多数説では、夫婦共有財産は、共有に属する個々の財産毎に個別に分割されるべきでなく、夫婦共有財産全体として分割される必要があり、夫婦財産の解消は財産分与手続によるべきであるとする。遺産共有の解消が、共有物分割によらず、民法906条の遺産分割手続によらなければならないとする判例と類似の考え方と言えます。
但し、離婚後2年間の申立期間を経過している場合や財産分与請求権がない場合等、財産分与手続によって処理できない場合は、物権上の持分に基づく請求は認められる余地があるようである。しかし、有形な寄与・経済的な寄与がある場合のみ訴訟では認められているように思われる。以下に、物権上の持分による共有を認めた裁判例を2例紹介する。
物権上の共有を認めた裁判例1(東京地裁判決昭和35年8月6日)
自宅不動産がオーバーローンの状態にあるため、離婚訴訟では、その帰属について判断しなかった為、結果的に夫名義のままとなった自宅不動産に居住継続した元妻に対するの元夫提起の明渡訴訟において、元妻の特有財産出捐による持分を認定して、明渡請求を棄却した。元妻の特有財産支出による不動産の共有持分を遡及的に認めた裁判例であり、下記判例を詳細にお読み下さい。
物権上の共有を認めた裁判例2(大阪高裁判決昭和57年11月30日)
内縁夫が死亡した場合に、内縁夫の相続人に財産分与義務が相続されず、死亡による内縁解消による財産分与は否定されます。
本裁判例は、内縁夫の単独名義の不動産について、相続人の子に対して内縁の妻が実質的持分の確認と更正登記を求めた訴訟で、内縁妻Xの請求を認容した。
内縁夫Aと内縁妻Xは昭和6年に挙式して同居したが、婚姻届は提出しなかった。昭和22年、AはBと浮気して子Yが出生。浮気相手に強く求められて婚姻届を出したが、その後も、内縁妻と同居し、昭和44年にAとBは協議離婚。Aは昭和54年に死亡し、遺産をYが相続。Xは不動産は、AとXが永らく協力して呉服商を経営してきた収入から取得したもの(Aの2年間の応召中は、Xが単独で経営)として、実質的持分の確認と更正登記を求めた。
裁判所は以下の通り判断した。
正式の婚姻関係であると、内縁関係にあるとを問わず、妻が家事に専従しその労働をもって夫婦の共同生活に寄与している場合と異なり、夫婦が共同して家業を経営し、その収益から夫婦の共同生活の経済的基礎と構成する財産として不動産を購入した場合には、右購入した不動産は、たとえその登記上の所有名義を夫にしていたとしても、夫婦間において、これを夫の特有財産とする旨の特段の合意がない以上、夫婦の共有財産として同人らに帰属するものと解するのを相当とする。
- 裁判例出所:家裁月報36-1-139
共有持分の確認請求に関する裁判例
実質的共有に関する物権的共有説に基づく裁判例は少なく、特殊なものに限られると言われているようです。以下は、婚姻中の共有持分を確認した裁判例である。
- 東京地裁判決昭和35年8月6日(法曹新聞156-9)
妻Xと夫Yは共働き夫婦で収入はほぼ同額。土地代金は、夫婦で貯めた預金から支出し、建物代金は連帯債務として弁済。(ローンはX名義口座から弁済)土地・建物共、夫名義としたが、Xは、Yと不仲となって別居中に、2分の1の持分移転登記を求めた。
裁判所の判断:「通常は、夫婦間の財産関係は、離婚時の財産分与の問題として精算されることが多いが、婚姻関係の破綻を離婚によって精算する以前の段階において、夫婦間の財産関係を明らかにするというのであれば、その権利関係を明らかにする利益を否定できない。XYの共有に属すると判断するのが相当。夫名義の現行登記は、権利の実態関係に合致しないもので、真実の権利関係に合致させるために、XはYに対する登記請求権がある。」
→夫婦間の経済的寄与の均等性に着目した判決と考えられるか? - 松山地裁判決昭和昭43年9月10日(判例時報536-73)
妻が、共稼ぎで購入した夫単独名義の不動産の共有確認を求めて認容。 - 札幌高裁判決昭和61年6月19日(判例タイムズ614-70)
夫婦が共同で貯めた資金等で購入した不動産について、家事労働等も含めた寄与割合で、共有持分権を確認し、更正登記手続を認容。
参照資料:「離婚に伴う財産分与ー裁判官の視点に見る分与の実務ー」松本哲泓著(新日本法規出版、2019年8月)