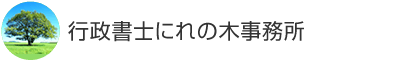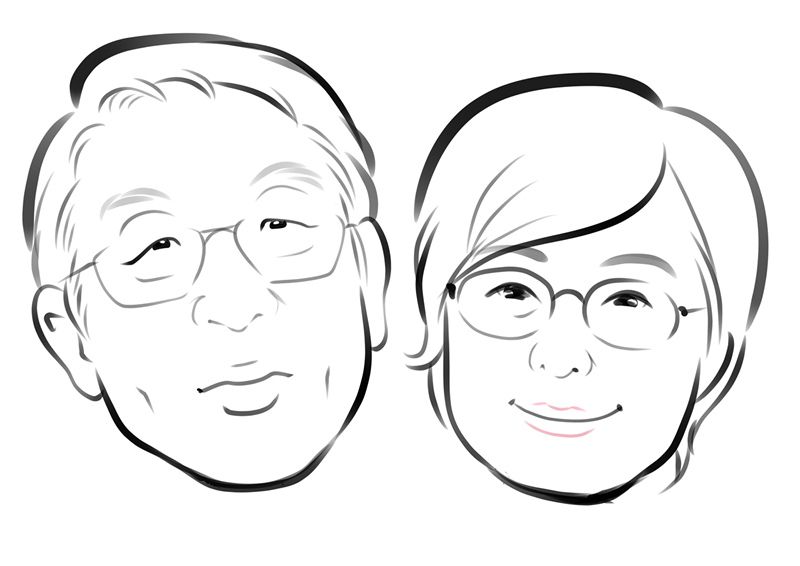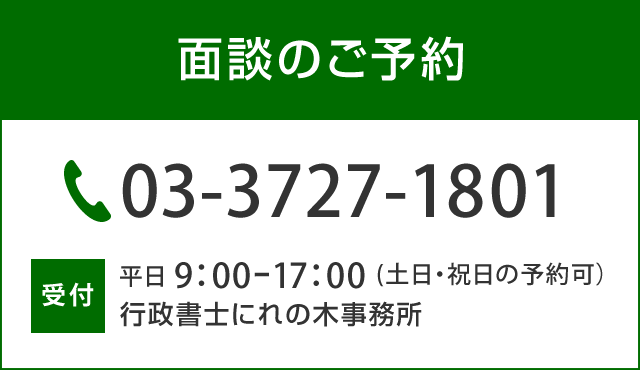民法915条では、熟慮期間は「自己のために相続が開始したことを知った時から三箇月」と規定され、この3ヶ月間で被相続人の財産状態を調査して相続の承認か放棄の選択することとされています。
しかし、特に被相続人との交流が殆どない等生活関係が希薄な場合等は、被相続人の財産状態、特に債務、とりわけ保証債務を調査することは困難を極めるのは当然ですから、熟慮期間の起算日をいつとするかが重大な法律的争点になり、心ならずも自己と直接関係のない多額の借財を負ってしまうという悲劇も少なくありません。
熟慮期間の起算日である「自己のために相続が開始したことを知った時」とは「相続の原因である事実(死亡等)を知った時及びこれにより自己が法律上の相続人となったと知った時」とする判例(大審院決定大正15.8.3、単に死亡等の相続開始の原因事実を知っただけで足りるとした判例を変更)が確立していて、これが熟慮期間の起算日の原則です。(兄弟姉妹等の第三順位の相続人は、前順位の相続人全ての相続放棄を知った時や相続債権者から催告や支払督促を受けた時が起算日となります。)
この原則に対する例外を認容すべきかどうかを争点に、昭和59年4月27日の最高裁判例が先例・リーディングケースとして確立しており、以下のように判示しています。(但し、判事5人中1人の反対意見あり。)
相続人は、相続開始後すぐに相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に全く相続財産がないと信じたためであり、被相続人との生活歴や交際状態等からみて相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人がそう信ずるについて相当な理由があると認められる時は、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである。
- 最高裁昭和59年4月27日判決文(出所:最高裁判所判例検索)
- 相続放棄の熟慮期間・起算日についての裁判例を集約して解説します
- 債務は法定相続分で自動的に承継ー積極財産の相続分とは無関係
- 相続放棄で債務から逃れる方法ー配偶者と子の場合を解説
- 相続放棄で債務から逃れる方法ー兄弟姉妹・直系尊属の場合を解説

事案の概要
被相続人Aは、昭和52年7月25日に準消費貸借契約上の債務について連帯保証した。債権者Xは、Aに対して保証債務の履行請求を求める訴訟を一審に提起し、昭和55年2月22日に認容判決が出たが、判決正本の送達前の昭和55年3月5日にAが死亡したため、訴訟は中断した。一審は昭和56年2月12日にAの相続人Y(妻と子3人)に訴訟を引き継ぐ訴訟手続の受継決定をして、同月に同決定と判決正本を送達した。これにより、Yは、Aの債務の存在を始めて知り、受継した訴訟を控訴すると共に、同月26日に大阪家裁に相続放棄の申述を行い、同年4月17日に受理された。
定職につかずギャンブルに熱中するAとの間で、Aの家族はいさかいが絶えず、昭和41年から42年にかけて妻と子3人は家出をして、以後AとYは没交渉となった。Aは、生活保護を受けながら単身で生活していたが、昭和54年夏から医療扶助を受けて入院し、昭和55年3月5日に死亡した。子の一人が民生委員から入院を知らされてAを病院に見舞うと共に、死に立会ったので、死亡翌日まで相続人全員がAの相続開始を知った。
当時、Aには相続すべき積極財産が全くなく、葬儀も行われずに遺骨も寺に預けられた事情にあり、入院前から係属していた訴訟についてはAからは何も知らされず、連帯保証債務の存在も知らなかったために、相続に関して何らかの手続をとる必要があることは全く念頭になかった。
裁判所の判断
Aの死亡の事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った当時、Aの相続財産が全く存在しないと信じたために、これらの事実を知つた時から起算して3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたものである。
Yが第一審判決正本の送達を受けて連帯保証債務の存在を知るまでの間は、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められる。
熟慮期間は、連帯保証債務の存在を認識した昭和56年2月12日等から起算されるべきで、Yが同月26日にした相続放棄の申述は熟慮期間内に適法にされたものである。これに基づく申述受理もまた適法であり、Yは連帯保証債務を承継していない。
相続人は、相続開始後すぐに相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に全く相続財産がないと信じたためであり、被相続人との生活歴や交際状態等からみて相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人がそう信ずるについて相当な理由があると認められる時は、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。
まとめ
相続放棄申述の熟慮期間の起算日は、原則、相続の原因である事実を知った時及びこれにより自己が法律上の相続人となったと知った時とするのが確立した判例です。
本判例が、熟慮期間の起算日について原則に対する例外を定めたリーディングケースとなっていますが、文字通り「相続財産が全くない」と信じた場合に限るという限定説と、一部相続財産の存在を知っていても通常は債務の存在を知れば当然相続放棄したであるような「債務が存在しない」と信じた場合も含まれるという非限定説があります。
訴訟は限定説をベースに解釈され、相続申述受理審判では非限定説をベースに運用されているという主張・言説もあるようですし、最高裁は限定説に立つという解釈もあるようです。
本訴訟を担当した最高裁調査官の解説は以下の通り。(最高裁判所判例解説民事篇昭和59年度P188)
悪質な金融業者が熟慮期間の仕組みを悪用して、故意に期間経過後に相続債務の取立てをするケースがある事や、一般的にも相続人に対し将来相続債務が出現することを予想して相続放棄をすることは酷であること、相続債権者側にも相続人の資力を当てにする利益はないということなどを考慮すべきである。
一方で、相続の確定が相続人の主観に左右されては、取引が不安定になるし、相続財産の調査をせずに軽率に相続財産がないと誤信した相続人を保護する訳にもいかない。
そこで、「相続財産が全くないと信じて熟慮期間を徒過したことに過失がない場合(相当な理由がある場合)には相続の開始を知ったとはいえない。」とする起算日の例外を採用した。「相当な理由」はかなり厳格に解されるが、核家族化の進んだ今日ではその事案も少なくないであろう。
尚、当時は、わざと3ヶ月経過後に催告するサラ金等の悪質な金融業者が相当多かったようです。現在がどうなっているか解りません。