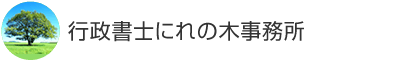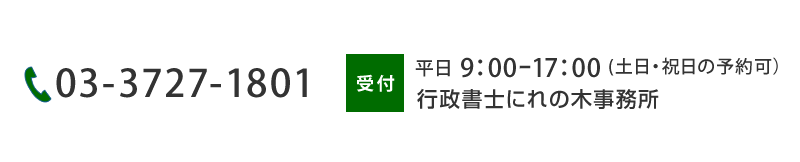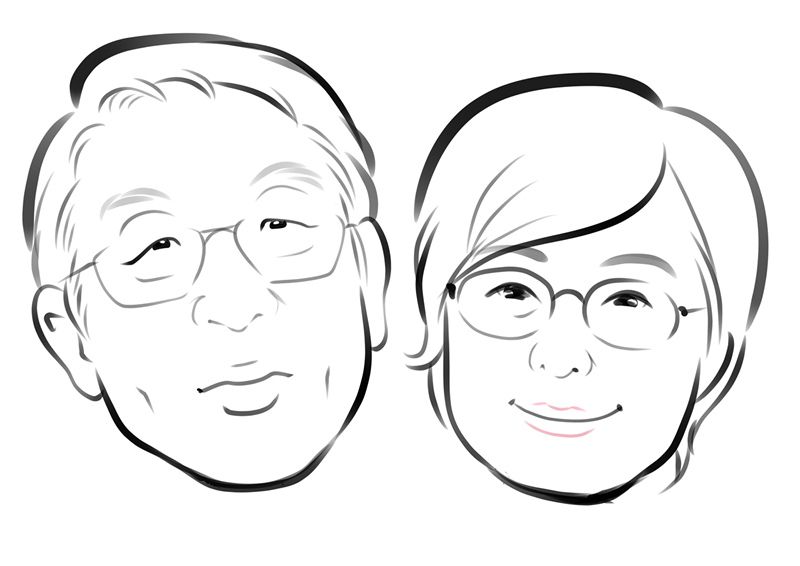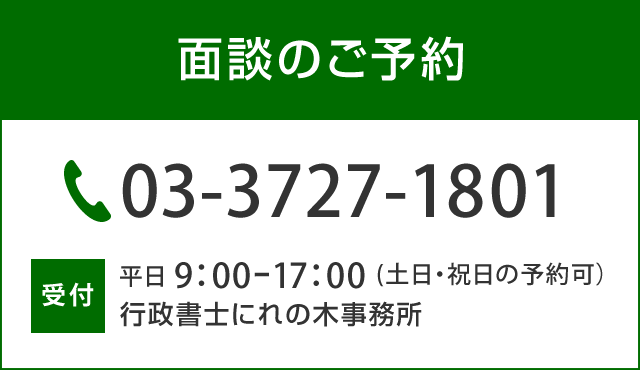札幌高裁平成19年6月26日決定。
定年退職の7年前から別居したこと及び定年退職後の7年間の家庭内別居をしたことは、保険料納付や掛け金の払い込みに対して元夫が特別な寄与をしたとは言えないとして、0.5の年金分割(合意分割)における按分割合を相当とする高裁決定。
夫婦同等の寄与として、年金分割についての請求割合を0.5とした。原審判である釧路家裁平成19年5月18日審判を是認し、元夫の即時抗告を棄却。
裁判例出所:家庭裁判月報59巻11号P186
- 年金分割の按分割合に関する裁判例を集約して解説します
- 年金分割・按分割合は、家裁審判では特別事情がない限り0.5(裁判例)(大阪高裁平成21年9月4日決定)
- 年金分割・按分割合は、35年の別居があっても0.5(裁判例)(大阪高裁令和元年8月21日決定)
- 0.3の年金分割の按分割合で確定した希な裁判例(東京家裁平成25年10月1日審判)
- 婚姻30年中、13年別居していても年金分割は0.5(裁判例)(東京家裁平成20年10月22日審判)
- 浪費や財産隠匿は、年金分割に関する特別事情にあたらない(裁判例)(広島高裁平成20年3月1日決定)
- 同居期間が短い事は、年金分割の特別事情にあたらない(裁判例)(名古屋高裁平成20年2月1日決定
- 年金分割しない旨の合意があれば年金分割しなくてもすむか?
- 年金分割をしない合意を有効として、年金分割審判を却下した裁判例(静岡家裁浜松支部審判平成20年6月16日審判)
- 年金分割ー離婚後に老後の所得保障を確保する必須手続
- 熟年離婚―退職金、家処分等の財産分与、年金分割が争点で、相続も解説
- 精算的財産分与ー夫婦間協力が終了する別居時を基準とする原則を解説
- 別居と婚姻費用ー別居を長くしても自動的には離婚できません。
-1024x683.jpg)
事案の概要
- 昭和46年婚姻
- 平成5年:当初は勤務先近くで同居していたが、高校がないので、都市部の中古住宅を購入して、妻子はそちらに居住。しかし、子が巣立っても、妻は、「田舎はいやだ」として一人で居住して別居状態に。
- 平成12年:夫が定年退職して、都市部の家に同居するも、家庭内別居状態(性交渉も妻が拒否)
- 平成18年3月:妻が家出(夫は、老後の貯蓄の全てをもって突然の家出と主張)
- 平成18年に夫は夫婦関係調整調停申立(趣旨・離婚)するも、妻は不出頭で不成立
- 夫が離婚訴訟準備中に、今度は妻側が夫婦関係調整調停申立(趣旨・円満調整)
- 平成19年調停離婚(婚姻36年)
- 平成19年元妻が年金分割の按分割合の調停(審判)を釧路家裁に申立て、0.5の審判。
- 元夫は、定年退職前に7年、定年退職後は、家庭内別居が7年もあるとして、札幌高裁に即時抗告。
高等裁判所の判断
- 婚姻期間中の保険料納付や掛金の払い込みに対する寄与の程度は、特段の事情が無い限り、夫婦同等とみ、年金分割についての請求割合を0.5と定めるのが相当。
- 抗告人(元夫)が主張するような事情は、保険料納付や掛金の払い込みに対する特別の寄与とは関連性がないから、特段の事情に当ると解することはできない。
- 原審判は相当であり、抗告は棄却する。
原審判(釧路家裁平成19年5月18日審判)
- 相手方(元夫)は、対象期間における保険料納付や掛金の払い込みに対する当事者の特別な寄与について、特段の主張及び立証をしていない。
- 相手方は、調停離婚時の約束に対して、申立人が不誠実な対応をすると申述するが、寄与の程度とは関連性がない。
- 被用者年金は、基本的に夫婦双方の老後のための所得保障としての意義を有しているので、特段の事情がない限り、夫婦同等とみるのが相当。
- 本件においては、特段の事情が認められない。
コメント
離婚時年金分割制度が平成19年4月1日に施行されて以来、最初の裁判例に近いのではないか。最高裁事務総局が、平成19年3月に示した一般指針とほぼ一致していると思われる。