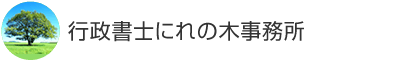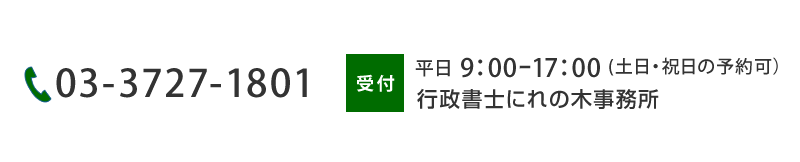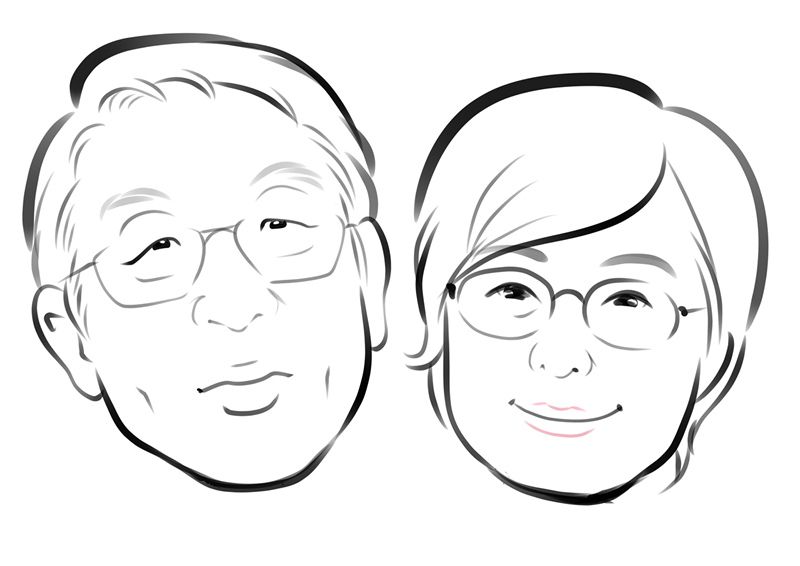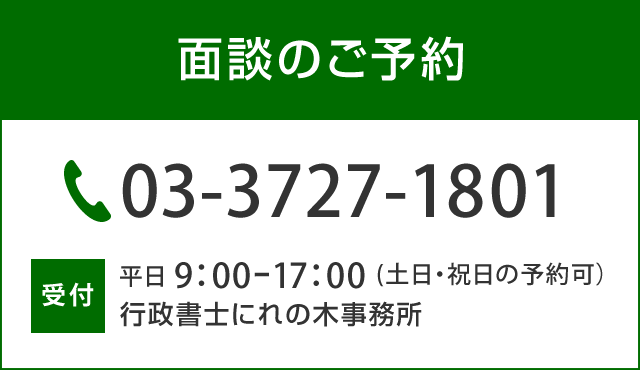公正証書遺言と法務局保管自筆遺言は、遺言者の死亡後に相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人であれば、無料や安価な費用で、比較的簡単に遺言書の有無を全国のいずれかの公証役場や法務局で検索できます。
検索後、公正証書については、保管している公証役場で公正証書正本又は謄本を取得でき(郵送請求も可能)、法務局保管自筆遺言については、どこの法務局でも遺言書情報証明書を取得できます。
公正証書遺言は、作成後直ちに、遺言者本人に正本と謄本が交付されるので、相続人が正本・謄本の保管場所を覚えている限り、謄本を取り直す必要はありません。正本・謄本とも紛失したり消失した場合でも、以下の手続きで、遺言者の死亡後であれば、相続人、受遺者等の利害関係人が、比較的簡単に正本又は謄本を再取得することができます。
一方、法務局保管自筆遺言は、作成後に公正証書遺言の謄本に相当する遺言書情報証明書が遺言者に交付されないので、遺言者の死亡後に、かなり煩雑な手続で遺言情報証明書をとる必要があります。

遺言の検索
公正証書遺言
- 検索可能な遺言:公正証書遺言検索システムが構築された平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言
- 検索時期:遺言者の死亡後
- 公証役場:どこの公証役場でも検索可能
- 検索できる者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①遺言者の除籍謄本、②相続人の戸籍謄本等利害関係人であることを証明する資料、③請求者の免許証等本人確認資料
- 費用:無料
法務局保管自筆遺言
法務局で、「遺言書保管事実証明書」の申請を行って、保管されている自筆遺言の有無を確認できます。但し、遺言内容については通知されません。
- 検索可能な遺言:2020年7月以降の保管分
- 検索時期:遺言者の死亡後
- 法務局:どこの法務局でも検索可能
- 検索できる者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①遺言者の除籍謄本、②相続人の戸籍謄本等利害関係人であることを証明する資料、③請求者の住民票の写し
- 費用:800円/1通
遺言書謄本等の取得
公正証書遺言
遺言公正証書の正本・謄本を紛失・消失した本人や相続人、遺言を見せることを拒まれた相続人等の利害関係者は正本又は謄本の取得が可能です。
- 時期:遺言者本人以外は、遺言者の死亡後
- 公証役場:原則、公正証書遺言を作成した公証役場。2019年4月1日より、郵送で公正証書の正本又は謄本の請求・受領が可能になりました。手続後述。
- 請求者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①被相続人の除籍謄本、②被相続人との相続関係を示す戸籍謄本等、③請求者の本人確認資料(免許証等)
法務局保管自筆遺言
保管時に、公正証書遺言のように正本・謄本は遺言者に交付されないので、公正証書の謄本に相当する遺言書情報証明書を遺言者の死亡後に交付請求す る必要があります。
- 時期:遺言者の死亡後
- 法務局:どこの法務局でも取得可能
- 請求できる者:相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人
- 必要書類:①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本全て②全相続人の戸籍謄本等(子が死亡していた場合は、孫が代襲相続人となるが、子の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本で代襲相続人の特定が必要)③全相続人の住所証明書(住民票の写、在留証明―海外在住の場合)
- 相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局の遺言書保管官は、他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知するために全相続人の住所証明書が必要。但し、遺言書の存在を知らせるのみで、遺言書の内容(=遺言書情報証明書)を通知する訳ではない。
郵送による公正証書遺言の謄本交付請求方法
- 保管先の公証役場に、検索結果を告げて「公正証書謄本交付申請書」を入手する。(メールで可能)
- 請求先の公証役場宛に郵送にて謄本交付請求を申請
- 郵送方法はレターパックのみ
- レターパックに入れて郵送する書類:①自署して実印を押印した「公正証書謄本交付申請書」、②印鑑証明書、③被相続人の除籍謄本、④被相続人との相続関係を示す戸籍謄本等、⑤請求者の本人確認資料(免許証はコピー、③④は原本必要であるが、原本還付可能)、⑥遺言公正証書検索結果、⑦返送先の住所・氏名及び電話番号を記入したレターパック
- 請求先の公証役場指定の口座に謄本交付手数料を事前納入。(2025年5月現在謄本一部2,000円程度ー遺言書の長さにより異なる)
- 公正証書謄本及び領収書がレターパックで届く