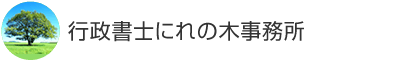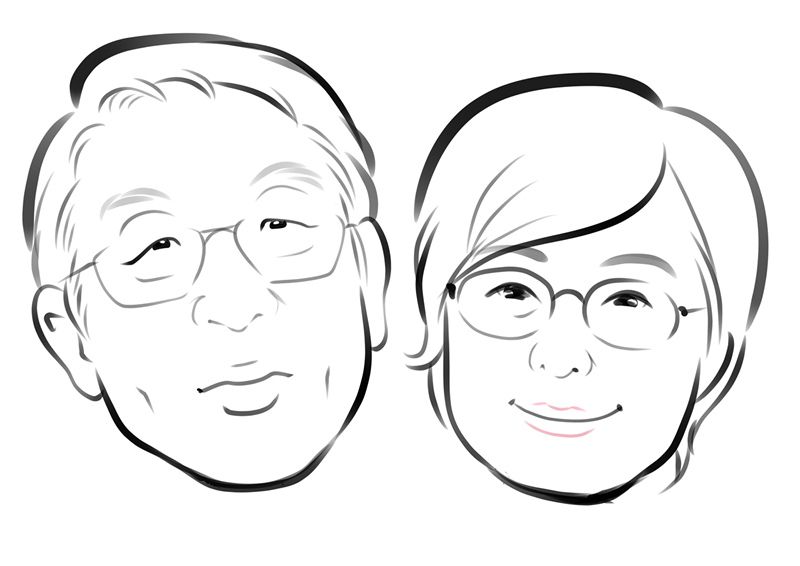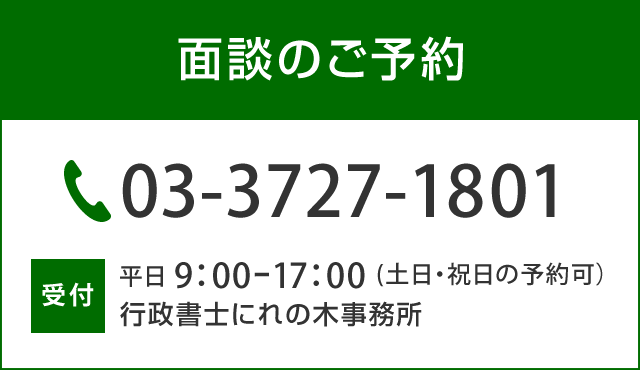遺言で住居等を妻に遺贈する場合は、「遺言者の妻である甲山乙子(昭和○○年○○日生)に、次の不動産を相続させる。」等の表現がよく使われます。しかし、遺言作成後に妻と離婚した場合に、この妻への遺贈条項は相続上どう取り扱われるのでしょうか。
あくまで妻という身分をもった甲山乙子と特定しているので、妻でなくなった以上、この条項は撤回されるという見方もあるでしょうし、自然人である甲山乙子に遺贈するので、妻でなくなっても甲山乙子に遺贈する意思であると読むこともできない訳ではありません。例えば、その住居が夫婦の共有であり、長い婚姻関係がある場合、配偶者という身分でなくなっても、夫の持分を甲山乙子に遺贈させるという意思の場合もあるでしょう。
公正証書遺言作成後に、離縁という身分行為で養子縁組が解消された場合、後の離縁という身分行為の生前処分行為が、前の遺言と両立しえないことが明らかである場合は、養子に遺贈するとした遺言は撤回されたものと見做すと判示した最高裁判例(最二判昭和56年11月13日)を紹介します。
民法1023条第1項は、前の遺言と後の遺言が抵触する場合は、前の遺言が撤回されたと見做すとの規定ですが、第2項で、遺言が遺言者の生前処分その他の法律行為と抵触する場合は、前項を準用すると規定しています。
1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言者の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
本裁判例は、第2項の法意は、遺言者がした生前処分に表示された遺言者の最終意思を重んじることにあり、抵触とは、単に、後の遺贈対象の不動産の売却など生前処分により前の遺言の執行が客観的に不能となるような場合にのみとどまらず、諸般の事情から後の生前処分が前の遺言と両立できない趣旨のもとにされたことが明らかである場合をも包むと判示して、遺言は、生前の身分行為である離縁により撤回されたと判断しました。
本判例に従えば、離婚という身分行為により、遺言は撤回されたと見做すという考え方もあるようには思います。しかし、必ずしも、身分行為という生前処分が前の遺言と両立しない趣旨のもとにされたことが明らかであるとは言い切れない場合も多いように思います。ポイントは、紹介した判例のように、身分行為という生前処分が、遺言と両立しないという事情が立証されるかどうかであり、極めてグレイな場合が殆どではないでしょうか。
やはり、離婚したときは、本条項は撤回すると明示されない限り、グレーであると思います。しかし、妻に相続させる遺言を作成する時は、通常は、夫婦関係が円満な場合であり、そういう時点で、「離婚した時は撤回する」と記載することは通常考えられません。遺言書作成後に別居や離婚した時は、離婚協議書に遺言書中の妻への遺贈条項は撤回するとの確認条項を入れるか、とりあえず、新たな自筆遺言を作成して前の遺言を無効とすべきでしょう。
別居期間が長く、諸般の事情からまだ離婚できないていない場合、全く配偶者に相続させない趣旨の遺言を書くのが通常です。しかし、希な例ですが、子との間で遺留分の争いが起きてほしくないという気持から、相手に一定程度の遺産を相続させる場合もあるようです。この場合こそは、「夫(妻)○○が、この遺言の効力発生時に遺言者の配偶者の地位を喪失していた場合は、夫(妻)○○に相続させるした財産を、△△に相続させる。」と明示で意思表示すべきです。

事案の概要
- D(明治27年3月10日生)はE(明治33年7月24日生)と婚姻したが、Eとの間では実子がおらず、Fとの間でただ1人の実子B1がいたが同居していなかった。
- DとEの夫婦は、昭和7年にDの実弟Gと養子縁組したが、Gの妻とEとの折り合が悪く10数年後に別居した。その後D夫婦は、昭和48年に実子B1と同居したが、B1の妻とEの折合いが悪く、7ヶ月後に別居した。
- その後Eが脳溢血で入院することもあり、終生老後の世話を託すべく、Eの実家筋からA夫婦を養子に迎えることを希望したが、当初A夫婦は難色を示した。Dから「実子B1には居住する不動産をやれば十分で、A夫婦がD夫婦の養子となってD夫婦を扶養してくれるなら、他の不動産を全部遺贈する」との申出を受けて、A夫婦は昭和48年1月22日(D78才、E72才時)にD夫婦と養子縁組して共同生活を営みD夫婦の扶養をした。
- DはAとの約束に従い、昭和48年1月28日付公正証書で「現金・預貯金全部は妻Eに遺贈し、不動産中B1が居住する土地をB1に遺贈し、その余の不動産全部をA夫婦に遺贈する」旨の遺言をした。
- ところが、昭和49年10月、Aとその実兄の訴外Iが経営していたJ株式会社が倒産し、A及びIが無断でD所有の不動産にJ会社のK信用金庫に対する4億円の債務担保のために根抵当権設定をしたことが発覚した。
- このことを知ったDは激怒したため、AとIは、6ヶ月以内に根抵当権設定登記を抹消して、DからのJ会社の借用金1500万円を返還する旨の念書をDに差し入れたが、念書は履行されなかった。
- D夫婦は、A夫婦に対する不信の念を深くして、昭和50年8月26日協議離縁をして、A夫婦はD夫婦と別居した。
- A夫婦は別居後も、D夫婦を扶養せず、B1夫婦がD夫婦の身の廻りの世話をしていたが、Dは昭和52年1月8日に死亡し、妻Eも同年2月1日に死亡した。
- B1らは、A夫婦に対して、公正証書遺言の無効を主張する訴えを提起した。
裁判所の判断
- 民法1023条1項は、前の遺言と後の遺言と抵触する時ときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす旨定め、同条2項は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する旨定めているが、その法意は、遺言者がした生前処分に表示された遺言者の最終意思を重んずるにあることはいうまでもない。
- 同条2項にいう抵触とは、単に、後の生前処分を実現しようするときには前の遺言の執行が不能となるような場合にのみとどまらず、諸般の事情より観察して後の生前処分が前の遺言と両立せしめない趣旨のもとにされたことが明らかである場合も包含するものと解するのが相当。
- 原審が適法に確定した事実関係(注:前記事案の概要)によれば、DはA夫婦から終生扶養を受けることを前提としてA夫婦と養子縁組したうえその所有する不動産の大半をA夫婦に遺贈する旨の遺言をしたが、その後A夫婦に対し不信の念を深くしてA夫婦との間で協議離縁し、法律上も事実上もA夫婦から扶養を受けないことにしたというのであるから、本件協議離縁は前に遺言によりされた遺贈と両立せしめない趣旨のもとにされたというべきであり、本件遺贈は後の協議離縁と抵触するものとして前示民法の規定により取り消されたものとみなさざるを得ない。
コメント
- 遺言の後の離婚・離縁等の身分関係の処分行為が、前の遺言と抵触するとして遺言の撤回を認定した最高裁判例である。
- 本件は、養子縁組の目的が終生扶養であり、それを前提に遺贈の遺言をしたことが証拠で明らかにされたので、民法1023条2項に言う後の協議離縁という法律行為が前の遺言と抵触すると認定されたものである。
- 夫婦遺言(夫と妻がそれぞれが作成する二つの独立した遺言)において、互いの全財産を夫又は妻に遺贈する(=相続させる)という遺言を書くことがしばしば見られる。
- しかし、遺言後に離婚した場合、上記のような遺言は取り消されずに有効なものとされるのかが問題となる。本判例は、養親縁組の目的と遺贈の関係が明確であると言えるが、一般的な離婚では身分関係継続の目的と遺贈の関係がそこまで明確と言えるか疑問なしとはしない。果たして、妻が終生夫の面倒を見るというようなことを遺贈の前提としていることが明確であろうか?
- 本判例は、遺言の目的が身分関係の解消等により法律的にも事実的にも果たされなくなったことが明らかである場合、前の遺言との抵触を認定して遺言の取消しを擬制したもので、離婚の場合も、一応、適用されるようには見える。離婚の場合にも自動的に適用されるか不明確であり、あいまいなグレーの領域は残る。
- 離婚した場合は本遺言を撤回する等の条項を遺言付加すれば明確になるが、夫婦仲が円満な時にそのような条項を入れる人は通常はいない。
- 離婚に至る前の別居時又は離婚後直ちに、まず自筆で遺言を撤回するか新たな遺言を作成するべきであろう。